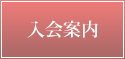第135回(2017年度秋季)大会プログラム
2017年09月05日
第135回(2017年度秋季)大会プログラムについて、冊子体はすでに会員の皆さんにお届けしております。下記は、ホームページ掲載版のPDFファイルです。ご活用ください。
第135回大会プログラム(ホームページ掲載版)<2017年9月11日修正版> 
なお、こちらのファイルでは、大会報告フルペーパーのダウンロードに必要となるIDとパスワードの書かれたページを削除しております。IDとパスワードについては、冊子体のプログラムをご利用ください。
――――
社会政策学会第135回大会プログラムにつきまして、すでにお送りいたしました冊子記載内容の一部に誤植がありました。下記の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。
該当箇所 p.6
書評分科会②貧困の志賀信夫会員のご著書の書名
(誤)『貧困研究の再検討 相対的貧困から社会的排除へ』
(正)『貧困理論の再検討 相対的貧困から社会的排除へ』
秋季大会企画委員会委員長 熊沢 透
ニューズレター2016-2018年期5号(通巻92号)を掲載
2017年08月31日
ニューズレター2016-2018年期5号(通巻92号)について、PDFファイルを掲載しました。会員の皆さんには、すでに冊子体をお届けしております。
No. 92 (2017. 8. 7)
第23回(2016年度) 学会賞選考委員会報告
2017年08月09日
【学術賞】
該当作なし
【奨励賞】
柴田 悠
『子育て支援が日本を救う 政策効果の統計分析』勁草書房、 2016 年 6 月。
学会賞選考委員会
岩永理恵、榎一江、大沢真知子、岡本英男、廣澤孝之(委員長)、枡田大和彦、森川美絵
1.選考経過
2016 年 10 月の幹事会で上記 7 名が選考委員に委嘱され、選考作業を開始するための委員会を 10 月 15 日に同志社大学今出川キャンパスで開催した。委員の互選により廣澤孝之を委員長に選出した後、選考の対象とする著作の範囲、選考方法、会員への周知方法などについて協議した。2016 年 12月 13 日付の Newsletter において、学会賞候補作の推薦(自薦・他薦)についてのお願いを会員向けに公示した。
第 1 回選考委員会を 2017 年 1 月 23 日に日本女子大学目白キャンパスで開催した。会員から自薦・他薦された著作に加えて、会員の著作と思われるリストを database より検索し整理したうえで、第一次審査として第二次選考の対象とする著作の絞り込みを慎重に行っていった。その結果、10 著作を第二次審査の対象とすることを決定した。
2 月 24 日に第 2 回選考委員会を日本女子大学目白キャンパスで開催した。第二次審査の対象とした 10 著作のなかから、学会賞として広く推薦・表彰するに値する研究内容や新しい視点を含んでいるか、今後の活躍が期待されるかなどを総合的に検討し、最終選考の対象として 3 著作を選出した。
第 3 回選考委員会を 4 月 15 日に法政大学市ヶ谷キャンパスで開催した。最終選考の対象となった 3 著作に対して選考委員全員がそれぞれの視点から講評を述べ、学術賞・奨励賞の対象に相応しい研究水準に達しているかについて、かなり詳細な検討を行なったうえ、奨励賞として上記の 1 著作を選定することに決定した。
2.選考理由
柴田悠『子育て支援が日本を救う 政策効果の統計分析』勁草書房、2016 年 6 月。
この著作において著者は、日本においては「社会保障の政策効果」の分析はまだ不十分であると指摘し、「経済成長率」「労働生産性」「出生率」「子どもの貧困率」「自殺率」などさまざまな社会指標に対して、子育て支援の諸政策がどのように影響するかを統計的に分析することを目標に、具体的な政策手段が及ぼす政策効果の因果関係について論証している。
統計分析は専門的かつ難解になりがちであるが、第 2 章の「使用データと分析方法」についても丁寧な説明がなされており、多くの人に開かれた議論が可能となる工夫がなされている。また論証に使用した OECD 統計など国際データは、誰もが入手可能なものであり、学術的な検証可能性・再現性も確保されている。さらに政策効果の因果関係を提示し、財政規模の予測にまで踏み込んだ検討をすることで、具体的な政策選択について、財政面を含めた実現可能性や優先度の検討を可能にしようとしている。そうした意味で、著者が意図する政治的立場を超えたエビデンスベーストな政策論に向けた手堅い「参考資料」の提供という課題は、かなりの程度実現していると評価することができる。
一方で本書における考察には、いくつかの問題点や残された課題も存在する。第一に、統計分析の手法の限界から、分析の視点が短期的なものに限定されていて、子育て支援という長期的な視点からも考慮すべき政策領域に対する分析としては物足りなさを感じる点。第二に、研究の前提となる説明、たとえば中長期的な日本経済の推移に対する考察は手薄で、景気変動や雇用政策などに対する見方に偏りが見られる点。その他のテーマに関しても仮説的・主観的な叙述が多く見られる点。第三に、著者が主張するように、日本が本格的に子育て支援に公費を投入すべき時期に来ていることは明らかであるが、なぜ日本は OECD 諸国のなかで子育て支援に大きく後れを取ってきたのかなどを考えたときに、国際比較データの分析だけでは日本社会の政策課題の特殊性が見えてこないのではないかという点。たとえば日本では女性の労働力率の増加が生産性の向上に結びついてこなかったとされるが、その問題の克服には子育て支援だけでなく別の政策課題が枢要な論点として存在するのではないか。第四に、著者が現実的な財源確保の方法として提言する「小規模ミックス財源」は、従来の政治学の蓄積を考えると、もっとも政治的抵抗力を受けやすく、およそ合理的でない歪な形に制度改変される可能性がある点。このように、本書は、明確な主張を繰り広げた裏返しとして、従来の研究蓄積や争点に対する目配りが不十分に感じられる面が少なくない。
以上指摘してきたいくつかの課題や問題点にもかかわらず、著者の本書での分析は首尾一貫しており、その明晰な論証は一定の説得力を持ち、本学会員の研究に大きな刺激を与えるものと評価できる。結論として選考委員会は、本書が政策提言をめぐって意義ある論争を巻き起こすインパクトを持った問題提起の著作として、奨励賞を授与するに値するものと判断した。著者が今後も社会政策の分野で幅広く活躍することを期待したい。
最後に、今回受賞には至らなかったが、最終選考の対象とした著作について、簡潔に講評を記しておく。
渡辺あさみ『時間を取り戻す 長時間労働を変える人事労務管理』旬報社、2016 年 3 月は、1990 年代以降の主としてホワイトカラー労働者の長時間労働の実態解明とその克服の試みを論じた著作である。時宜を得た研究テーマであり、人事労務管理のフレキシブル化への対抗力の必要性を説く論旨には大いに説得力がある。しかし、全体的に先行研究に依拠した部分が大きく、事例研究が 1 社にとどまるなど、研究の完成度にやや物足りなさが感じられ、残念ながら奨励賞には至らなかった。
筒井淳也『結婚と家族のこれから 共働き社会の限界』光文社、2016 年 6 月は、共働き社会の実現がそれだけは社会の安定につながらず、家族主義からの離脱が必要であるとする論旨は明快であり、多くの人に読んでほしい好著である。私的領域に公正性を徹底させることの困難性の指摘や、税制と家族モデルをリンクさせる政策論などは多くの示唆を与える。ただし読みやすさを重視した一般書であるため、典拠資料等が詳細に示されていないなど、学術賞を授与するには躊躇せざるを得なかった。しかし、家族や結婚という社会政策がこれまで周辺的に論じてきたことの重要性を意識させる著作として高く評価できる。
(文責:廣澤孝之)
第14回東アジア社会政策会議のお知らせ(国際交流委員会)
2017年07月11日
社会政策学会会員各位
8月2~3日に名古屋大学豊田講堂で第14回東アジア社会政策会議(East Asian Social Policy Research Network Annual Conference)を開催します。
テーマは「変わりゆく環境のなかの東アジア社会政策――比較・構想・未来」です。
基調講演は無料公開します。施世駿(国立台湾大学)、落合恵美子(京都大学)、サラ・クック(ユニセフ・イノチェンティ研究所)、広井良典(京都大学)の各氏による興味深い講演が予定されています。
会議本体を聴講希望の方はこちらから参加登録をお願いします(7月23日締切。参加費は弁当・懇親会込で一般10000円、院生2000円です)。
充実した内容の114報告が予定されていますので、ぜひ御参加下さい。
社会政策学会 国際交流委員会
日本経済学会連合「平成29年度学会補助募集のお知らせ」
2017年06月13日
本学会が加盟する日本経済学会連合では、外国人学者招聘滞日補助、国際会議派遣補助、および学会会合費補助を募集しています。
応募要項等詳しくは、ホームページをご覧ください。
社会政策関連学会協議会シンポジウム(2017年6月24日)
2017年05月25日
社会政策学会会員各位
本学会が加盟する社会政策関連学会協議会主催のシンポジウム「経験者が語る修士論文完成まで」が6月24日、明治大学グローバルフロント1階グローバルホールにて開催されます。
参加費無料、参加予約不要、当日先着順です。
このシンポジウムでは、修士論文の研究テーマの選定、課題設定をどのように行ったのか、研究方法を具体的にどのようにしたのか、その方法をめぐって悩んだことや、どのように解決したのかについて、留学生院生や社会人院生の経験も含めて、「修士論文完成まで」をご報告いただきます。
会員の皆さまにおかれましては奮ってご参加ください。
◆シンポジウムチラシ
社会政策学会幹事・社会政策関連学会協議会協議員 阿部誠・藤原千沙
本学会英文ニューズレター(2018年3月刊行予定)への報告英文アブストラクト掲載について
2017年05月25日
重点事業担当幹事 平岡公一
秋季大会企画委員会委員長 熊沢 透
社会政策学会会員各位
現在、社会政策学会の「重点事業」である英文ニューズレターの刊行に向けて、幹事会で準備を進められているところです。そのコンテンツとして、現在は学会HP上で公開されている各報告の英文アブストラクトをあらためて掲載することが予定されています。
秋季大会企画委員会では、第135回大会の自由論題報告とテーマ別分科会の募集の詳細は4月6日づけでHP上に公開いたしましたが、その時点では英文ニューズレターへのアブストラクト掲載の件はお知らせしておりませんでした。
報告申請をお考えの会員各位には遅れたお知らせとなりましたことをお詫び申し上げるとともに、ご申請の際にご用意いただく英文アブストラクトを英文ニューズレターに再掲させていただくことをご了解くださいますようよろしくお願い申し上げます。
なお、この件につきましてご意見やご要望がございましたら、秋季大会企画委員会委員長 熊沢 kumat [at] econ.fukushima-u.ac.jp([at]を@に変えてください)までご連絡くださいませ。
以上です。
第134回大会のフルペーパーの電子配布はこちらから
2017年05月24日
部会名称のリンクをクリックした先のページからダウンロードしてください。
・電子ファイルの事前配布はテーマ別分科会と自由論題です。
・公開は2017年6月18日(日)までです。
・ミラーサイト(予備サイト)はこちらです。同じファイルがDLできますので、学会サイトからDLできないときご利用下さい。
第134大会・大会2日目・フルペーパー(午前の部 09:30~11:30)
2017年05月24日
<テーマ別分科会・第1>
今日の労使関係の動向と課題 〔一 般〕
座 長・コーディネーター:木下武男
1.2000年代における製造業派遣・請負労働の労使関係
今野晴貴(一橋大学・院生)<報告ファイル>
2.裁量労働制を規制する労使関係の実態
三家本里実(一橋大学・院生)<報告ファイル>
3.ブラック企業に対抗する労使関係の構築
青木耕太郎(東京大学・院生)<報告ファイル>
<テーマ別分科会・第2>
韓国におけるベーシック・インカムの構想 〔日本・東アジア社会政策部会〕
座長:阿部 誠(大分大学)
コーディネーター:金 成垣(明治学院大学)
討論者1:田多英範(流通経済大学)
討論者2:岡本英男(東京経済大学)
1.不平等時代における福祉国家の有用性とベーシック・インカムの可能性
金 敎誠(中央大学[韓国])<当日配布>
2.なぜいまベーシック・インカムなのか――韓国における不安定労働市場と社会保障制度の不整合
李 承潤(梨花女子大学)<当日配布>
<自由論題・第1 社会的排除>
座 長:大西祥惠(國學院大學)
1.貧困世帯の子どもの学習支援に関する先行研究・理論・仮説についての研究
松村智史(首都大学東京・院生)<報告ファイル>
2.学生における相対的剥奪の検討
谷川文菜(首都大学東京・院生)<報告ファイル>
3.公衆衛生の対象としての精神障害者支援
酒本知美(日本社会事業大学)<報告ファイル>
<自由論題・第2 社会政策・共済>
座 長:畠中 亨(帝京平成大学)
1.1980年代の農林年金の動向
福田 順(同志社大学)<報告ファイル>
2.シルバー人材センターの最近の停滞と新たな成長への模索
小澤一貴(法政大学・院生)<報告ファイル>
3.大河内一男のヴェーバー解釈と「学としての社会政策」
田中良一<報告ファイル>
<国際交流分科会 日韓交流セッション>
地域包括ケアの日韓比較:介護保険給付と保険給付外の地域基盤型サービスや支援の組合せによる包括ケアへの動向と課題(韓国社会政策学会との交流セッション、保健医療福祉部会と国際交流委員会との共催)(日本語および韓国語の日本語への通訳で実施)
〈座長〉田中きよむ(高知県立大学)
〈コーディネーター〉長澤紀美子(高知県立大学)
〈討論予定者1〉井口克郎(神戸大学)
〈討論予定者2〉金 智美(慶南大学校)
1.日本における地域包括ケア政策・研究の課題
鶴田禎人(同朋大学)<Download >
2.Governing Long-Term Care Policies in South Korea and Japan
Jooha Lee(Dongguk University, Korea)
Sang Hun Lim(Kyung Hee University, Korea)<Distribution on the day>
3.A study on the expansion of the care services for the elderly and the role of local authority in Korea
Yongho Chon(Incheon National University, Korea)
Haemi Park(Daejeon University, Korea)<Distribution on the day>
第134回大会・大会2日目・フルペーパー(午後の部 12:50~14:50)
2017年05月24日
<テーマ別分科会・第3>
ジェンダー視点から見た日本・韓国・ドイツにおける有期雇用の実態と変化
〔非定型労働部会、ジェンダー部会〕
座 長:渡邊幸良(同朋大学)
コーディネーター:横田伸子(関西学院大学)
1.ジェンダーの視点から見た日本の有期・非正規雇用
三山雅子(同志社大学)<当日配布>
2.ジェンダーの視点から見た韓国の有期雇用の実態と変化
横田伸子(関西学院大学)<当日配布>
3.ドイツにおける有期雇用の特徴
田中洋子(筑波大学)<報告ファイル>
<テーマ別分科会・第4>
福祉の市場化――韓国と中国を例にして―― 〔一 般〕
座 長・コーディネーター:埋橋孝文(同志社大学)
討論者:李 蓮花(静岡大学)
1.韓国における社会福祉政策の市場化に対する批判的評価
李 宣英(江南大学)<当日配布>
2.中国における介護の市場化・産業化の背景と動向
郭 芳(同志社大学)<報告ファイル>
3.中国の介護市場化における民間事業者像
史 邁(同志社大学・院生)<報告ファイル>
<自由論題・第3 アクティベーション>
座 長:石川公彦(広島国際大学)
1.東日本大震災復興と公的職業訓練――認定職業訓練を中心に、震災後6年目の検証――
木村保茂(北海学園大学)<報告ファイル>
2.地域都市における自立・就労・生活支援の実践とその課題
梅崎 修(法政大学)<報告ファイル>
3.デンマークの公的扶助受給者への「教育援助」導入の背景と経過
加藤壮一郎(熊本市都市政策研究所)<報告ファイル>
<自由論題・第4 日韓の高齢者ケア>
座 長:石井まこと(大分大学)
1.高齢者介護に関する白書の語りの分析
角 能(東京大学)・張 継元(日本女子大学)<報告ファイル>
2.高齢者ケアサービス提供体制の市場化に関する日韓比較
金 智美(慶南大学校)<報告ファイル>
3.ケアの市場化におけるケアワークの統制:日韓における家族介護への支払いの展開からの示唆
森川美絵(国立保健医療科学院)<報告ファイル>
<国際交流分科会 ESPAnet-JASPS Joint Session>
Part I: Labor Market
Chair: Charles Weathers: Osaka City University
1.Minimum wages as social policy: a comparison of policy change in Germany and Japan since the early 2000s
Steffen Heinrich: German Institute for Japanese Studies (DIJ)<Download>
2.Photographs of generations on the labor market
Ioana van Deurzen and Sonja Bekker: Tilburg University, The Netherlands<Download>
3.Bribery and Labour Market
Yoshihiko Fukushima: Waseda University, Japan<Download>
« 次のページ
前の記事 »
![]()