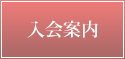2020年05月19日
本部・事務局から
最新の記事
- 国際学会報告助成・海外研究者招聘助成(国際交流委員会)
- 産業労働部会の設立準備委員会発足
- ニューズレター122号(2025.7.15)を刊行しました。
- 第151回(2025年度秋季)大会の自由論題報告、テーマ別分科会の募集について
- 第151回(2025年度秋季)大会の自由論題報告とテーマ別分科会の募集期間などについて
アーカイブ
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年9月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年12月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年4月
- 2011年10月
第140回大会 共通論題フルペーパー
第140回大会・大会2日目・フルペーパー(午前の部 9:30~11:30)
2020年05月11日
<テーマ別分科会・第7>
大学教職員の不安定就業問題 〔労働組合部会、非定型労働部会〕
座 長:伊藤大一(大阪経済大学)
コーディネーター:髙野 剛(立命館大学)
1.アメリカ高等教育の不安定な労働権利
チャールズ・ウェザーズ(大阪市立大学) <報告ファイル>
2.ドイツにおける大学教職員の雇用構造
田中洋子(筑波大学) <報告ファイル>
3.専業非常勤講師という問題
上林陽治(公益財団法人地方自治総合研究所) <報告ファイル>
4.労働者代表の可能性:36協定による専任教員の過重労働の規制と非常勤講師の雇用・労働条件の確保
今井 拓(日本大学) <報告ファイル>
<テーマ別分科会・第8>
若者の「自立」を問い直す
―特に困難な状況にある若者の労働、住居、家族の課題― 〔一般〕
座 長・コーディネーター:岩田正美(日本女子大学名誉教授)
1.自立援助ホームに入居する若者の労働問題に関する質的調査
渡辺寛人(東京大学・院生) <報告ファイル>
2.ワーキングプアの住居喪失と労働住宅の利用―宮城県ハウジングプア調査をもとに―
三家本里実(立教大学) <報告ファイル>
3.精神疾患を抱える若者の自立と家族関係―ケース記録とインタビューの分析を通じて―
今岡直之(NPO法人POSSE) <報告ファイル>
<自由論題・第5 理論・概念>
座 長:石塚史樹(東北大学)
1.福武直のヴェーバー解釈と社会政策学
田中良一(無所属) <報告ファイル>
2."social security"から「社会保障」へ―翻訳をめぐる試行錯誤―
菅沼 隆(立教大学) <報告ファイル>
3.社会政策の集合行為論的解釈における「協力」概念の意味
高橋 聡(岩手県立大学) <報告ファイル>
<自由論題・第6 障害・共生>
座 長:石川公彦(沖縄大学)
1.社会福祉における「公共性」概念の変遷について:供給システムに着目する
孫 琳(同志社大学・院生) <報告ファイル>
2.自治体住民相談事業にもとづく生活支援ニーズの実態把握
泉田信行(国立社会保障・人口問題研究所)・白瀬由美香(一橋大学) <報告ファイル>
3.障害者サッカーにおける指導者活用推進施策の質的検討
近藤沙耶(桐蔭横浜大学・院生)、田中暢子(桐蔭横浜大学) <報告ファイル>
第140回大会・大会1日目・フルペーパー(午後の部 15:00~17:00)
2020年05月11日
<自由論題・第3 貧困・ジェンダー>
座 長:鬼丸朋子(中央大学)
1.シングルマザーと公的年金―年金加入の実態を中心に―
吉中季子(神奈川県立保健福祉大学) <報告ファイル>
2.日本の高校生のフード・インセキュリティ―貧困との関連に着目して―
近藤天之(東京都立大学・院生)、阿部 彩(東京都立大学)、梶原豪人(東京都立大学・院生)、
小山 宰(東京都立大学・院生)、栗原和樹(一橋大学・院生)、瀧澤宏直(東京都立大学・院生)、
湯 承晨(東京都立大学・院生)、張 秀賢(東京都立大学・院生) <報告ファイル>
3.高校生アルバイトの探索的研究―貧困とジェンダーの視点から―
川口 遼(東京都立大学子ども・若者貧困研究センター) <報告ファイル>
<自由論題・第4 所得保障>
座 長:畠中 亨(帝京平成大学)
1.都道府県レベルの分娩費用の変化に関連する要因の探索的検討
小暮かおり(東京大学) フルペーパー提出無し
2.住宅手当導入の政策効果:マイクロシミュレーション分析
田中聡一郎(関東学院大学)、渡辺久里子(国立社会保障・人口問題研究所)、山田篤裕(慶應義塾大学)
<報告ファイル>
3.繰上げ受給・資格期間短縮化が老齢年金受給者に与えた影響
山田篤裕(慶應義塾大学) <報告ファイル>
第140回大会・大会1日目・フルペーパー(午前の部 9:30~11:30)
2020年05月11日
<テーマ別分科会・第2>
「就労支援政策」の国際比較―日本の特質を考える― 〔一般〕
座 長:垣田裕介(大阪市立大学)
コーディネーター:阿部 誠(大分大学名誉教授)
1.韓国における国民基礎生活保障と自活事業
松江暁子(国際医療福祉大学) <報告ファイル>
2.ドイツにおける就労困難者向け就労支援政策の現状と課題
森 周子(高崎経済大学) <報告ファイル>
3.日本の就労支援の特質
阿部 誠(大分大学名誉教授) <報告ファイル>
<自由論題・第1 労働・政策>
座 長:チャールズ・ウェザーズ(大阪市立大学)
1.若者政策と若者運動の日韓比較―若者政策体系を中心に―
朴 在浩(東京都立大学・院生) <報告ファイル>
2.ワークフェアの分析視角―国際比較研究と日本への含意―
小林勇人(日本福祉大学) <報告ファイル>
3.私立中・高等学校における非正規雇用問題の研究―労使紛争調査および雇用システム論の分析視角から―
今野晴貴(NPO法人POSSE) <報告ファイル>
<自由論題・第2 ケア供給>
座 長: 遠藤希和子(立正大学)
1.ケアの倫理と社会政策——日本の障害者政策への示唆―
鈴木知花(一橋大学・院生) <報告ファイル>
2.社会政策としての幼児教育・保育の無償化に関する一考察―認可外保育施設をめぐる議論に着目して―
松村智史(東京都立大学) <報告ファイル>
3.中国とタイにおける高齢者ケアシステムの構築:中/低所得国における制度構築の現状と課題に着目して
三好友良(HelpAge International Asia Pacific Regional Office) <報告ファイル>
140回大会web事前登録のお知らせ
2020年05月09日
社会政策学会 会員の皆様
社会政策学会 第140回大会の共通論題は、ZOOMウェビナーによるオンライン開催となります。以下のURLにて、ウェビナーに事前登録してください。
あなたはZoomウェビナーに招待されました。
開催時刻:2020年5月24日 12:30 PM 大阪、札幌、東京
トピック:社会政策学会第140回大会共通論題
このウェビナーに事前登録する:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pPABFZbPTZyrdvx4NNtkFg
ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
共通論題 質問フォーム。
以下の入力フォームより、登壇者に対する質問を入力してください。
(ZOOMウェビナーの「チャット」機能は使わないでください)
入力フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQvow51r8cjvDqqHojOGj65cu53PHgevUV0K5YvgvafXFMrQ/viewform

ジェンダー部会からのお知らせ
2020年04月29日
【ジェンダー部会からのお知らせとお願い:社会政策学会 研究環境調査】
社会政策学会 会員各位
ジェンダー部会では、よりよい研究環境の構築に向けて、このたび社会政策学会会員の皆様を対象に、オンライン調査「社会政策学会 研究環境調査-2020年ハラスメント調査」(調査期間:5月7日-31日)を実施いたします。
追記:調査期間が6月10日まで延期になりました。
調査結果については2020年秋に開催される第141回共通論題「仕事の世界における権力構造とハラスメント(仮)」にて報告する予定です。
5月7日以降、【社会政策学会 研究環境調査へのご協力のお願い】の表題にて、本調査のウェブアドレスと回答パスワードを配信させていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
呼びかけ人:ジェンダー部会歴代世話人(五十音順)
伊藤セツ、居城舜子、 大沢真理、大槻奈巳、 清山玲、 竹内敬子、萩原久美子、服部良子、三山雅子、室住眞麻子、湯澤直美
ジェンダー部会連絡先:jasps.gender[at]gmail.com
[at]を@にかえて連絡下さい。
社会政策学会第140回大会の「開催形式変更」について
2020年03月31日
社会政策学会 会員のみなさまへ
新型コロナ感染の急激な拡大に伴い,東京都立大学で行う第140回大会について協議を重ねてまいりました.会員の安全と感染拡大防止を重視し,以下のような「開催形式変更」が決まりましたので,大会実行委員長,春季大会企画委員長,学会代表幹事より会員のみなさまにお知らせします.この決定は2018-20年期幹事会の了承を得ています.
(1)2020年5月23日(土)・24日(日)に東京都立大学で予定していました第140回大会は,安全と感染拡大防止を重視し,会場に参集しての形式では行いません.
(2)共通論題については,オンライン形式での開催を予定しています.
(3)テーマ別分科会および自由論題につきましては,ホームページ上での報告フルペーパー掲載による開催とします(報告フルペーパー提出をもって報告したものとみなします.締め切りは5月6日(水)17時です.詳細は学会ニューズレターNo.6通巻101号をご参照ください.なお,テーマ別分科会については,討論者のコメントペーパーも提出していただきます.)
(4)若手研究者優秀賞のフルペーパーの選考は予定通り行います.
(5)予定していました教育セッションは中止します.
(6)予定していました総会は,秋の大会時(2020年10月24日・25日,立命館大学びわこ・くさつキャンパス)に行います.
(7) 共通論題,テーマ別分科会,自由論題の各報告タイトル,報告予定者,報告要旨および報告フルペーパーのダウンロードの方法については,近日中にホームページ上にプログラムを掲載いたしますので,そちらをご参照ください。
学会参加者の安全確保に最大限つとめ,また,感染拡大の防止に万全を尽くすために,参集する形を避け,インターネット等を活用した開催方式に変更することについて,なにとぞご理解いただきたいと思います.また,報告予定者のみなさまには,このような形式で報告いただくことをご了承いただき,報告フルペーパーの準備等を進めていただきますようお願い申し上げます。さらに,教育セッションをご準備いただいた方には,中止とすることについてご理解いただければ幸いです.
以上,まずは速報としてご連絡差し上げます.
2020年3月31日
第140回大会実行委員長 阿部 彩
春季大会企画委員長 鬼丸朋子
社会政策学会代表幹事 埋橋孝文
ニューズレター2018-2020年期7号(通巻102号)を掲載
第140回大会に関する重要なおしらせ
2020年03月08日
【重要なお知らせ】
社会政策学会会員のみなさま
今般、コロナ・ウィルス感染への対応のために、イベント等の自粛が求められております。
現時点においては、社会政策学会は、5月23日、24日の第140回大会(於・東京都立大学)を計画通りに開催する予定でおります。報告予定者の方は報告準備をおすすめくださるようお願いします。
しかしながら、今後の状況によっては、予定の変更などを余儀なくされる可能性もございます。
その際には、事前に、会員への一斉メールおよび学会ホームページにて、会員のみなさまにお知らせいたします。
2020年3月8日 社会政策学会代表幹事 埋橋孝文
国際交流委員会からのお知らせ
2020年02月05日
世界社会学会社会政策部会(ISARC19)から報告募集が届いています。
開催日は12月3~4日、報告要旨の締切は5月31日です。
来年度の国際学会報告助成の対象になりますので、ふるって御応募下さい。
The 2020 Annual Conference of the ISARC19
Call for papers and panel proposals
https://2020-rc19.webnode.tw/home2
http://www.rc19.org
Globalization in Retreat? Welfare States amid Regional Turbulence
03-04 December 2020, National Taiwan University, Taiwan
Deadline for abstracts and panel proposals: 31 May 2020
The contemporary prevalence of globalization has posed a grave challenge for the welfare state on all fronts. This phenomenon has attracted much attention from the policymakers and social policy analysts across the globe. The debates have focused primarily on whether, and to what extent, globalization impacts social inequality and social policy in individual countries. One of the major controversies in these debates concern whether globalization has a positive or a negative effect on welfare state sustainability. While some authors maintain that globalization leads to a decline in both the welfare state and the state’s regulatory capacities, others argue that the state actually expands social policy to support disadvantaged groups who bear the brunt of globalization.
The common starting point of these contrasted perspectives is the belief in the enduring influence of globalization on both public policy and human well-being. Yet, recent developments appear to challenge this consensus. Regional turbulences are beginning to generate counter-mobilizations that are calling globalization into question. Anti-immigrant sentiments have been contributing to the rise of populism in the past decade, of which the most spectacular event is the 2016 Brexit referendum in the UK. Meanwhile, the trade wars between China and the United States drag on, foreshadowing the ongoing and future competition between these two rival super powers. Social protests in Hong Kong further plague the already strained relations between China and the Western world. Trade protectionism and geo-political tensions are stirring the fear that the economic globalization of the post-war era may come to a halt. All these developments seem to indicate the advent of a new era in which the globalization as we knew it is facing a “great transformation.” The impact of this “great transformation” on the welfare state remains to be examined.
Against this background, the 2020 annual conference of the Research Committee 19 (on Poverty, Social Welfare and Social Policy) of the International Sociological Association (RC19) invites contributions that assess the changing contexts of globalization and its backlash; and analyse the impacts of shifting global and local politics on contemporary social inequalities and social policies.
More specifically, we very much welcome theoretical and/or empirical contributions exploring how specific social programs interact with changing political, economic, and social settings traditionally associated with globalization. Beyond the theme of the conference, we also encourage the submission of contributions within the field of comparative social policy. Finally, it is a long tradition of RC19 to invite papers by both PhD students and early-career researchers and established scholars working in the field of welfare state and social policy analysis.
The RC19 annual meeting brings together international scholars in the fields of comparative and transnational social policy studies, encompassing a range of disciplines including sociology, social policy, political science, and economics. Beyond the specific themes outlined above, RC19 members present their ongoing work and new papers, even if they are not closely connected to the theme of the conference. All presenters must be members of RC19 by the time of the conference. To join, please contact our treasurer, Timo Fleckenstein.
Keynote speakers (confirmed):
Professor Ann Orloff, Northwestern University, United States
Professor Lutz Leisering, Bielefeld University, Germany
Professpr Huck-ju Kwon, Seoul National University, South Korea
Those wishing to present a paper should submit an abstract of about 250 words. Information enclosed with any abstract should include: stream number, title of paper; author name(s); affiliation(s); and email address of one corresponding author.
Submissions for the annual RC 19 conference should be sent to: rc19taiwan@gmail.com. The deadline for abstracts and panel proposals is 31 May 2020.
Important dates:
Submission of abstracts and panel proposals: 31 May 2020
Notification of applicants: 20 June 2020
Early booking & registration will start from 21 June 2020
Further details about the conference programme and venue will be announced shortly. For any queries, please contact Chung-Yang Yeh at rc19taiwan@gmail.com. Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy RC19 of the International Sociological Association (ISA) brings together an active and lively community from different fields of social sciences. The purpose is to promote theoretically grounded empirical research on: the sources and character of social problems; the planning and administration of social programmes; and more generally, public policies and intervention strategies aimed at alleviating social problems and influencing the society in that regard.