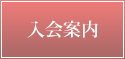Book Review Session(program) (SSSP 127th Biannual Conference)
2013年09月02日
1 Thoughts and History
Coordinator: Makoto Ishii(Oita University)
・Reiko Kaneda,
Magosaburo OHARA: a Business Administrator with Warm Heart & Cool Head
Reviewer: Naho Sugita(Doshisha University)
・Mayumi Oshio,
“Intoku”,The Thought on Poor Relief of Wealthy Merchant : Philanthropy in Edo era
Reviewer: Naoko Tomie(Ibaraki University)
・Naoki Fukuzawa,
History of German Social Insurance: Emergence and Development of “Sozialstaat”
Reviewer:Chikako Mori(Saga University)
2 Social Policies in Overseas
Coordinator: Hideaki Kikuchi(Musashi University)
・Yumi Matsumoto,
Historical Evolution of the French Healthcare System
Reviewer: Takaaki Odama(Japan Society for the Promotion of Science )
・Kenzo Yoshida,
Pension System in the United States
Reviewer: Takehiro Negishi(Kokugakuin University)
・Nobuko Yokota,
The Urban Under-stratum and Workers in Korea: Focusing on Non- Standardization of Labor
Reviewer: Akira Suzuki(Hosei University)
3 Welfare and Labor
Coordinator: Koh Igami(Kobe International University)
・Hiroshi Ohyama,
Formation of Social Policies and Role of the Nation: Aiming for Establishment of Practical Policies
Reviewer: Koichi Hiraoka(Ochanomizu University)
・Shogo Takegawa,
Policy-Orinented Sociology: Welfare State and Civil Society
Reviewer: Makoto Kono(Hyogo University)
・Koichi Matsuo,
The White-Collar Labor Market and School Career
Reviewer: Yuji Hayashi(Tokyo Metropolitan University)
Plenary Session(abstract)(SSSP 127th Biannual Conference)
2013年09月02日
Plenary Session : Housing Security and Social Policy
Coordinator: Shogo Takegawa(Tokyo University)
1 Housing policy and the reproduction of home ownership
(Yosuke Hirayama,Kobe University)
By the late twentieth century, following the sustained development of property ownership, home-owning society has effectively become ‘mature’ in Japan. This implies that great emphasis was placed on the reproduction of home ownership, rather than its creation. Since the 1990s, however, economic decline has combined with neoliberal transformations in government housing policy to undermine the reproductive capacity of Japan’s homeowner society. The contemporary housing situation of Japan is now raising questions as to the extent to which home-owning societies can be maintained, and whether a ‘post-home-owning society’ will emerge or not. Private ownership in Japan continues to occupy the main position as the dominant housing tenure. Japan’s home-owning society will therefore be likely to be maintained in the foreseeable future. However, home ownership in present-day Japan is completely different from what it was before. For the past two decades, most owner-occupied houses have consistently generated capital losses and an increasing number of homeowners have been trapped in negative equity. Moreover, younger generations are now increasingly being excluded from conventional routes that could take them into property ownership. This paper explores transformations in Japan’s home-owning society, placing particular emphasis on the role played by neoliberal policy in eroding the traditional system of reproducing home ownership.
2 A change of living capital and habitation poverty
(Yoshihiro Okamoto, Chukyo University)
Japan’s habitation is holding unbalance called the surplus and the housing poor of a residence today. This report catches the present habitation poverty through the change of the “living capital” which pulls out the structure supporting a life from society, and it presents the suggestion to a habitation policy.
”Living capital” consists of the following four sides. Thus, they are “the appropriate space which underpins a life based on a dwelling”, “the appropriate economic burden of housing expenses”, “conformity to the life stage of living environment”, and “participation for forming living environment suitable for a life.” This “living capital” changed at various points with change of economic society and a regional structure, and habitation poverty actualized.
This report mainly considers the relations between living capital and “working”, and “a welfare measure.” Although the dwelling is indispensable to a life, the income by working supports a security and maintenance of the dwelling. “The relation between a dwelling and working” has changed in response to the influence of the change of the urban infrastructure, industrial structure, and technology.
It analyses the relation also including the commercialization degree of a dwelling with the geographical relation between a place of work and a dwelling, and considers the positioning of a dwelling again.
Moreover, when it takes homeless issue, it shows the structure of the housing acquisition in which stoppage of an income loses an accommodation easily. And it is shown that the occurrence of the event in lives such as advanced age, the illness, the disabled unemployment and a disaster triggers the habitation poverty.
Furthermore, although the focus for measures moves from the institution to the local in aging, change of a family composition, and the medical treatment and the welfare makes the role of an appropriate dwelling conspicuous, it shows that the dwelling in the area is insufficient for supporting a life of all people.
At last it works on the measure which supports the “living capital” construction which realizes appropriate habitation for a broader meaning of homeless issue.
3 The Housing Problem for People in Need of Care and New Approaches to Dealing With It
(Lisa Kuzunishi, Osaka City University)
The circumstances of family relationships and lifestyles in relation to communities are changing by the hour and by the day. Due to the rise in divorce rates, increases in the number of people who have become single once again, and in single-parent households, are showing a consistent upward trend. The trend towards late marriages or never marrying at all is rapidly accelerating, and the choices to not marry or to not have children are no longer particularly unusual. Even for those who are married, where both partners are employed, there are families that do not live together due to the demands of work. The custom of children looking after their parents is in decline, and there is a conspicuous increase in households consisting only of the elderly. Due to changes like these in the forms of families, and ideas about what families should be, it has become difficult to manage care-giving issues such as housekeeping, child rearing, and nursing of the elderly and invalids within the bounds of traditional families. Even without urgently pressing problems of care-giving, the bonds with families and communities are being lost and there are many people living alone who have become isolated.
Among these, the single-parent households that are the focus of this paper are typical cases where the burden of child rearing is linked to difficulties in finding and keeping employment, and consequently to vulnerable livelihoods. For single parent households where one person has to take on the dual burdens of both employment and child rearing, private child rearing assistance is essential to help supplement the inadequacies of public day care. Where this cannot be secured, the reality is that there is a high probability of being excluded from steady employment.
In recent years, attention has focused on ‘shared housing,’ a living pattern where households who are not related by blood live together and through communal activity try to solve the concrete issues of living such as child rearing and housekeeping.
In this paper, I will first present an overview of the problems related to living and livelihood for single parents, and then next will describe case studies of shared housing aimed at single parents that have been verified within Japan.
4 British Housing Policy and Social Security Reform
(Michihiko Tokoro, Osaka City University)
Housing policy is a core in social policy and Britain has presented interesting developments in this area. The post-war welfare state provided council housing nationwide, and then, Margaret Thatcher’s government implemented ‘right to buy’ programme under her privatisation policy. While public sectors housing provision declined, cash benefits to support the tenants grew since the 1980s. Current coalition government aims to cut the social security benefits, in particular, targeting the housing benefit. It is feared that the recent policy changes would lead further difficulties for those with housing needs.
Analysis of British housing policy offers a good platform for social policy debates, including the role of state, market, cash benefit and social housings to fulfil the citizen’s basic needs. It is also important to examine the outcome of housing policy in the context of social exclusion. My paper will try to suggest the direction for Japanese social policy by evaluating the British policy developments.
第19回(2012年)学会賞 選考委員会報告
2013年07月22日
第19回(2012年)学会賞選考委員会報告
学術賞
該当なし
奨励賞
福澤直樹『ドイツ社会保険史: 社会国家の形成と展開』名古屋大学出版会
横田伸子『韓国の都市下層と労働者: 労働の非正規化を中心に 』 ミネルヴァ書房
吉田健三『アメリカの年金システム 』 日本経済評論社
第19回(2012年)学会賞選考委員会報告
委員 猪飼 周平 禹 宗杬 土田 武史 服部 良子(委員長) 平岡 公一
1 選考経過
2012年10月の幹事会で上記5名の選考委員が委嘱された。
学会賞の対象となる文献の選定にあたり、ニューズレターと学会ホームページにおいて自薦、他薦を募ったところ、それぞれ1点ずつの推薦があった。また、2012年12月末にワールドプランニングから会員名簿を取り寄せ、大型書店のデータベースを用いて2012年1月から12月までの間に刊行された会員の著書を検索し、そこから会員暦3年以上の会員の単著とされる77点を選び、その文献リストを各委員に送付した。
第1回選考委員会を2月7日に早稲田大学で開催した。最初に、学会の選考規程に照らして文献リストの点検を行い、単著でないもの、教科書、法令集などをリストから除外し49点が選考対象となった。選考対象の文献ごとに2名の委員に担当を割り振ったうえ、次回の選考委員会までにそれぞれ候補作をリストアップし持ち寄ることとした。また、重ねて選考にあたっては学会規程と慣例に基づいて行うことを確認した。なお確認に際しては、土田委員のお骨折りにより選考対象作の実物のうちの大半が委員会席上に準備頂けたため迅速かつ正確な審査が可能となった。
第2回選考員会を3月10日に早稲田大学で開催した。リストアップした49点の作品について、各担当の2名の審査結果をもとに一点ずつ審査を行い、学術賞および奨励賞の最終選考にかける作品として、あわせて8点を選考した。またこの時点で最終選考候補作とするかどうかについて確認を要するものとして1点が残った。その採否についてはメール等で連絡を行い、次回に最終確認をすることとした。
次回の選考委員会までに最終候補作品の全てを各委員が精査し、学術賞および奨励賞のそれぞれ受賞候補作について検討結果を持ち寄ることとした。
第3回選考委員会を4月18日に早稲田大学で開催した。先の選考委員会で最終選考にかけるかどうか決定していなかった1点について検討を行い、対象から除くこととした。最終選考に残った8点について、学術賞および奨励賞について検討した結果、学術賞については該当なし、奨励賞として3点の著書を選考した。
2 選考理由
奨励賞の3点についての選考理由は以下の通りである。五十音順に掲載する。
福澤直樹『ドイツ社会保険史-社会国家の形成と展開』名古屋大学出版会は、ドイツの社会保険について、その形成から1990年代まで(主として1970年代まで)の展開過程を分析したもので、ドイツ社会保険に関する本格的な歴史研究として評価できる。古くて新しい重厚な論点から出発しており、その意味では社会政策の基礎にかかわる著作である。ドイツ社会保険の歴史的展開のなかでの重要な局面、研究史上の重要な論点について、掘り下げて検討している。文献と一次資料を丹念に検討した上で、わかりやすく図表化していることや、豊富な文献研究にあとづけられた叙述がなされていることなど、資料の渉猟と分析における豊富な投下労働がうかがわれる。また、社会保険を歴史貫通的に見ることで「福祉国家(社会国家)に内包される共同体的性質ないし連帯性の歴史的に裏付けられた論理」を検証するという分析視角が基本にあるものと思われ、異なるレベル・枠組みの連帯性の間の関連や国家の積極的な機能の発現などの観点で政策展開が意味づけされている。歴史研究と政治学・社会学的研究のアプローチの違いということであろうか。本書に続く今後の研究成果が期待される。
その一方で本研究の目的が本書によってどのように達成できたかについては不明瞭な印象も残る。とくに本書の副題となっている「社会国家」に関して序論と第6章で触れられているだけで、成立についてもその後の展開についても特に言及されていない。副題にもかかわらず、社会国家についてのまとまった議論を欠いていること、また政治学・社会学の福祉国家研究に批判的に言及する一方、それに代わる理論枠組みは提示されていないことが惜しまれる。
横田伸子『韓国の都市下層と労働者: 労働の非正規化を中心に 』(ミネルヴァ書房)は、経済成長の本格化した1960年代から現代に至るまでの韓国の労働市場の構造を分析している。すなわち「分断的労働市場」という視点に依拠し、大企業・重化学工業・男性生産労働者という中核労働者の内部労働市場と、中小企業労働者をはじめとする周辺労働者の外部労働市場からなる分断的労働市場体制をなすとする韓国労働市場の実態と歴史的推移などを包括的に分析したものである。すなわち韓国において1960年代後半から80年代初めにかけて大量の離農民により形成された「都市無許可定住地」の就業者の特性として、都市インフォーマルセクターとフォーマルセクターの間を頻繁に往復する交流関係をとらえ、都市下層の形成過程と開発年代の労働市場構造をあきらかにしている。資料の制約の大きい中、実証のために、主要統計の原資料や多様な文献にあたるとともに図表の利用が巧みであることを評価したい。
ただ終章での総括的な議論が実証研究の知見を整理の後、「新しい労働運動モデル」の簡単な提示にとどまり、理論的な総括や「労働市場構造」の展望の議論がみられなかったのはやや物足りない。また、日本の先行研究との関連についてはかなり論じられているが、韓国の学会での研究に対する本書の貢献について、著者の考えるところは読み取れないことが惜しまれる。
吉田健三『アメリカの年金システム (アメリカの財政と分権) 』(日本経済評論社)は、アメリカの社会保障年金と企業年金の歴史的展開の検討をふまえて、「年金システム」の全体像を明らかにしようとしている。とくに「福祉資本主義」モデルとしての企業プラン(アメリカ・モデルの原型)が破綻したことをペースにして、その後の展開過程をアメリカ・モデルの隘路を克服する過程として描いている。また、エリサ法の生成と展開過程を克明にたどっており、401Kに連なっていく論理が明確にされている。この分野については既存の研究が多いが、歴史的な一貫した視点で考察したことは評価できる。さらにブッシュ政権の提案などこれまでほとんど触れられてこなかった事柄についても丁寧な分析が加えられ、アメリカの社会保障年金をめぐる動向が明確にされている。
アメリカの年金システムを、社会保障年金と企業年金(雇用主提供年金)の「公私二層システム」としてとらえ、それが、前者の基礎的保障の論理と後者の受給権保障の論理で構成される政策論理に支えられてきたものとみなし、このシステムが「福祉資本主義」の年金の消失リスクと、任意性の限界への対応から発展してきたとみる。このシステムが「福祉資本主義」の年金の消失リスクと任意性の限界への対応から発展しているとするのが著者の視点である。一貫してこの視点にそくして分析がおこなわれている。ただジェンダー問題や雇用政策との関連などの考察がない。また、福祉国家レジーム論によるアメリカ福祉国家のとらえ方への批判については課題が残る。
受賞作の選定には至らなかった学術賞ならびに奨励賞候補作について若干の講評を記しておく。
玉井金五『共助の稜線』(法律文化社)は、前著『防貧の創造』以降の論文を収録した論文集であり、アジア視点からの日本の社会政策の捉え直し、日本の社会保障政策の特質の解明、〈労働〉系と対比される〈福祉〉系社会政策論の意義の確認、〈経済学〉系社会政策論と〈社会学〉系社会政策論の系譜の解明、〈都市〉社会政策論特に「大阪での社会政策の実験」の検討などが主題となっている。そのなかに近現代日本の社会政策(論)の特質の解明という問題関心が一貫して存在している。
全体に広い視野からの議論が展開され、斬新な発想からの多くの貴重な問題提起を含んでいる。とくに90年代以降の日本経済と日本社会が直面している課題を、格差・貧困と国民皆保険・皆年金体制としての「財政調整」型社会保障とする点は日本型社会政策の特質として深めるべき課題の指摘である。また、20世紀の日本の福祉システムと社会政策の変遷の考察のなかからアジア間比較の座標軸を提起している分析は貴重である。ただ収録論文のもともとの性格もあって、個別の論点、たとえば、〈労働〉系と対比される〈福祉〉系社会政策論の共通のルーツ、相互の交流・交錯などについて掘り下げた議論がなされていない場合があるのが惜しまれる。
鈴木和雄『接客サービスの労働過程論』(御茶の水書房)は、日本ではこれまで本格的研究が少なかった「接客サービス労働」について、主としてアメリカの研究成果を用いて考察している。接客サービスの労働過程を、接客労働の3極関係、感情労働、労働移転の3つの問題に即して、理論的に分析、検討した研究の集大成といえる。接客サービス労働を分析するにあたって、こうした重層的分析をとることで接客サービス労働の特性と変化が明確にされている。とくにアメリカの研究成果から感情労働の役割が接客労働の理解にとって決定的重要性を持つという著者の主張が明確にされる。
本書の長所は、先行研究をふまえ、接客労働を取り巻く諸状況、および諸関係の概念を綿密に検討していることである。かなりの部分を社会学的な労働研究に依拠し、それを労働過程論の枠組みに取り込もうとしている。ただし、概念の検討において、労働をめぐる階級的対立という観点が直裁に投影され、積極労働、統制などの概念についての分析が十分に行われていない点が残念である。また労働市場や労使関係を捨象して労働過程に集中し、日本の実態をふまえた検討あるいはアメリカ、日本などの社会的/歴史的文脈を考慮しない分析がどこまで有効かという疑問も残る。
近藤克則『「医療クライシス」を超えて:イギリスと日本の医療・介護のゆくえ』(医学書院)は、イギリス医療改革の考え方と成果をふまえて、日本の医療制度危機からの脱却の方途を論じている。国際的医学雑誌にみる健康格差研究の成果、イギリスの医療改革についての的を射た理解と解説、日本の医療改革についての議論の展開は評価に値するが、立場の明快さに対して議論の客観性に疑問が残るとする意見があった。
所道彦『福祉国家と家族政策』(法律文化社)は、他分野での議論をふまえた家族政策の概念・枠組みの検討にもとづき、90年代~2000年代のイギリスの家族政策を概観し分析している。イギリスの給付パッケージを用いた国際比較で、イギリスの(特に労働党政権期の子育て支援策が低所得者層に手厚いという特徴が明らかになった点が注目される。また日本の家族政策に対して示唆するところも多い。ただし、本書の中心である英国の家族政策の検討が分析的というよりは概して叙述的で、著者自身が認めるように「流れの整理」にとどまっているところは惜しまれる。また、家族および家族政策の概念の検討から最近の研究にいたるまで、イギリスの家族政策を多角的に論じていくとき、福祉国家論や福祉国家の家族政策を論ずる際、90年代以前が少ない点が気になる。50年代までさかのぼって社会政策の争点の検討がなされるなら90年代以降の問題が明確になるとおもわれる。
以上が本審査委員会の選考の経過および結果である。最後に、第19回(2012年度)学会賞選考委員会開催と進行にあたり、前年度にひきつづき委員会会場提供をはじめ会議準備、選考対象文献リストの作成、さらには実物文献の調達準備などの多大な労をとられた土田武史委員に謝意を表する。
「役員選挙のお知らせ」の一部訂正
2013年07月16日
会員の皆さま
いつも学会活動にご協力をありがとうございます。
学会ニューズレター(紙面およびHPリンク上)にて、「役員選挙のお知らせ」をお送りしておりますが、文面の「人数」につきまして一部訂正がございます。
□訂正箇所:学会ニューズレター75号、1頁、「役員選挙のお知らせ」の第6項・2~3行目
(正)今回の選挙で幹事の被選挙権を有しない会員は次の6名である。
(誤)今回の選挙で幹事の被選挙権を有しない会員は次の4名である。
皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
末筆になりますが、選挙へのご協力をあらためてお願い申し上げます。
社会政策学会事務局 山田和代
第33期(2014~16年)役員選挙のお知らせ
2013年06月28日
今年は学会役員選挙が行われます。2014 年春季大会にて開催される総会から2 年間、「総会から総会までの間、本会の重要事項を審議する」(会則第14 条)幹事と会計監査を選出します。幹事会は、社会政策学会の次期役員の選挙を実施するために、2013 年6月21日付で、次の4 名に選挙管理委員を委嘱することにしました(「役員選挙に関する規程」第3 条)。
東北・北海道ブロック 宮本章史
関東・甲信越ブロック 森ます美
関西・東海北陸ブロック 新井美佐子
九州・中国四国ブロック 横田伸子
上記の選挙管理委員は、互選により新井美佐子を選挙管理委員長に選出した後、選挙日程と選挙に関する手続きを、以下のように決定しました。
1.選挙公示日:2013 年8 月21 日(水)
2.選挙の方法
①有権者の資格は、前回と同様の基準による扱いとする。すなわち「2011年度までに入会されている会員については2010 年度までの会費が納入されていること、2012 年度以降に入会された会員については入会年度の会費が納入されていること」とする。
②選挙管理委員会は、選挙公示後直ちに、投票用紙、有権者名簿、推薦文等を全会員に郵送する。
③投票は、有権者による投票用紙の郵送によって行い、投票の締め切り日を2013 年9 月30 日(月)(必着)とする。
④郵送投票の宛先は、本学会の事務センターがある「(株)ワールドプランニング」とする。
3.開票日、開票場所:2013 年10 月12 日(土)に大阪経済大学にて開票する。
4.選挙結果の発表:2013 年10 月13日(日)に社会政策学会臨時総会において行う。
5.役員の選出に関する推薦文:「役員選挙に関する規程」第7 条により、役員選出のために会員を推薦することを希望する会員は、以下の要領で推薦文を全有権者に配布することができる。
①賛同する会員5 名以上が署名した推薦文1 部を、2013 年7 月31 日(水)(必着)までに下記宛へ郵送する。
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学 国際言語文化研究科 新井美佐子
②推薦文は、署名者の氏名を含めて600 字以内とする。
③あわせて、推薦文のテキスト・ファイルを7 月31 日(水)までに、arai@nagoya-u.jp(新井美佐子)宛E-mail で送る。
④選挙管理委員会は、推薦文を全会員に配布する。
6.「社会政策学会会則」第13 条の規定によれば、幹事は連続3 期を限度としている。今回の選挙で幹事の被選挙権を有しない会員は次の6名である。
石井まこと、佐口和郎、菅沼隆、田中洋子、久本憲夫、矢野聡
また「社会政策学会会則」第18 条の規定によれば、会計監査は連続3 期を限度としている。今回の選挙で会計監査の被選挙権を有しない会員はいない。
<選挙にご協力を>
1) 会員にとって最も重要な学会活動の一つは、役員選挙です。これまでも投票率の低さが指摘されています(前回は、有権者数1,277名に対し、投票数は169件、投票率は13.8%でした)。学会活動をさらに活性化するためにも、何卒、ふさわしいと思われる方を積極的に役員に推薦し、またぜひ投票されますようにお願い申し上げます。
2) 今回のニューズレター(第4号、通巻75号)には一部の会員に会費の<再請求書>を同封いたしております。選挙権にも関わりますのでご注意下さい。
選挙管理委員長 新井美佐子
秋季大会の自由論題・テーマ別分科会報告応募を締め切りました
2013年06月14日
学会員のみなさまへ
開催校ともども万全の準備で会員の方々の大会参加をお待ちしておりますので、奮ってご参加ください。
なお、大会プロフラムのHP掲載ならびに発送は8月下旬を予定しております。
秋季大会企画委員会・委員長
第126回大会におけるLeón教授の特別講演の報告要旨とフルペーパー
2013年05月23日
大会プログラム要旨集に未掲載のDr. Margarita León (Universitat Autònoma Barcelona) による特別講演 “The participation of women in the labour market and childcare investment: views from Europe” の報告要旨とフルペーパーを下記に掲載いたしますので、ご利用ください。
フルペーパーのダウンロードはここから 
報告要旨:
One of the most important changes that have taken place in European societies since the 1960s and 1970s has been the incorporation of women to paid employment. The industrial economy pretty much built around male workers has given way to a service economy changing jobs and also workers. These changes in employment together with changes in the role of women has brought about a wide number of tensions and conflicts in modern European societies. This presentation will firstly focus in the tensions that exist between the participation of women in paid employment and fertility looking at changing dynamics and existing tensions in both female employment and fertility. Secondly, the presentation will analyze developments in childcare provision (Early Childhood Education and Care – ECEC) within the framework of a proposed paradigmatic change of welfare states through ‘social investment’. The presentation will give an overview of the current academic and political debate around the pros and cons of expanding service provision for small children (that is, children under compulsory school age).Developments in ECEC at least at the European level have certainly been backed up by a vast amount of research that prove, albeit with different emphasis, positive links between investment in ECEC and (1) female labour force participation, (3) fertility dynamics (3) children’s opportunities in life and (4) productivity imperatives in the knowledge-based economy. Despite the fact that causal connections are very difficult to identify (Gerda & Andersson 2008), it truly exists strong empirical evidence on the connections between the labour market participation of women –specially mothers with under school age children- and availability of childcare provision and/or other family-oriented policies (Kamerman & Moss 2009; Boje & Ejnraes 2011). Family policies oriented towards female employment –such as availability of public childcare- have a positive impact on levels of female employment (Gauthier, 2007) and vice-versa. However, there are significant differences between European countries not just in levels of ECEC coverage but on aspects related to the quality of the provision. Furthermore, it is important to look at ECEC development within broader policies for the reconciliation of work and family life, mainly forms of flexible but secured employment and parental leave schemes. The presentation will finally give an overview of the present challenges and dilemmas that European countries face nowadays with expanding ECEC services in the context of strong austerity social and economic programmes that the EU is imposing on member states as a response to the economic crisis.
第127回大会 自由論題報告、テーマ別分科会報告の募集(募集は締め切りました)
2013年05月11日
※ 報告の募集は締め切りました(2013/06/14)
社会政策学会第127回大会は、2013年10月13日(日)と14日(月)に大阪経済大学を大会実行委員会として、大阪経済大学(大阪市東淀川区)で開催されます。
秋季大会企画委員会では、同大会で開かれる自由論題およびテーマ別分科会での報告を募集しています。報告をご希望の方は、下記の要領でご応募ください。
なお、10月13日(日)を自由論題およびテーマ別分科会にあて、10月14日(月)は、終日共通論題にあてます。
■自由論題報告
自由論題での報告を希望される会員は、学会のホームページからダウンロードした応募用紙に、報告タイトル、所属機関とポジション、氏名(ふりがな)、連絡先(住所、電話、Fax、E-mailアドレス)、400 字程度のアブストラクト、専門分野別コード(1.労使関係・労働経済、2.社会保障・社会福祉、3.労働史・労働運動史、4.ジェンダー・女性、5.生活・家族、6.その他)等の必要事項を記入のうえ、添付ファイルとして下記の共通応募E-mailアドレスにご応募ください。
メールにて応募の際は、必ず、メールの件名に「自由論題報告(応募者氏名)」と明記をお願いします。
自由論題報告応募用紙
http://sssp-online.org/127freeapl.doc
応募先・問い合わせ先
jiyuusyuuki[at]yahoogroups.jp
( [at]を@に直して下さい)
なお、論文、あるいは他の学会報告等のかたちで既発表の報告の応募は、不採択といたしますのでご注意ください。また、自由論題に応募資格があるのは、会員で、当該年度まで会費を納入されている方です。
当日は、報告25 分、質疑10 分となります。
■テーマ別分科会報告
テーマ別分科会の企画を希望する会員は、学会のホームページからダウンロードした応募用紙に、分科会タイトル、分科会設定の趣旨(400 字程度、非会員を報告者に招聘するときは、招聘しなければならない理由を記入)、座長・コーディネーターの氏名(ふりがな)、所属機関とポジション、連絡先(住所、電話、Fax、E-mailアドレス)、報告者の氏名(ふりがな)、所属機関とポジション、E-maiアドレス、各報告のアブストラクト(400 字程度)、予定討論者の氏名(ふりがな)、所属機関とポジション等、必要事項を記載のうえ、添付ファイルとして下記の共通応募E-mailアドレスにご応募ください。なお、テーマ別分科会の企画に応募資格があるのは、会員のみです。
メールにて応募・問い合わせの際は、必ず、メールの件名に、「テーマ別分科会(部会名ないし分科会名・コーディネーター氏名)」を明記してください。
テーマ別分科会報告応募用紙
http://sssp-online.org/127themeapl.doc
応募・問い合わせ先
themesyuuki[at]yahoogroups.jp
( [at]を@に直して下さい)
■自由論題・テーマ別分科会の応募に共通の注意事項
(1) 応募は、原則として、学会ホームページからダウンロードした応募用紙に必要事項を記入し、添付ファイルとして、上記のE-mailアドレスにお送りいただくことになっています。しかし、コンピューター環境が整っていない場合は、上記の通りの必要事項をもれなく記載して、下記の秋季大会企画委員会委員長宛に郵送でお送りいただいても結構です。
(2) 応募用紙の「趣旨」「アブストラクト」の字数をお守りください。記入の不完全なもの、字数の著しく過剰なものや過少なものは、応募を不採択とさせていただくことがあります。
(3) 学会ではホームページを通じて、海外へも学会報告の情報を発信することにしています。そのため、応募用紙に英文で報告タイトル、アブストラクトを求めております。なお、学会として、ネイティブ・チェックとはしませんので、各自でご確認をお願いします。
(4) 応募にあたっては、2013年5月13日(月)現在の所属機関とポジションをご記入ください。大会プログラムには、原則として所属機関のみを表記しますが、院生の場合は所属機関とポジション(院生)を表記します。その後変更となる方は、報告時のフルペーパーに新しい所属機関などを各自がお書きくださることで、変更にご対応ください。
(5) 応募用紙に、タイトルおよび報告者の氏名・所属機関・ポジションの英語表記を記入していただくことになっていますので、ご留意ください。
(6) 応募の締め切りは、2013年6月13日(木)です。郵送の場合は当日必着です。締め切りは厳守です。その後の応募は不採択とさせていただきます。
(7) 応募された方に対しては、締め切りから1 週間以内に応募用紙受理の連絡を行います。この時までに連絡のない場合はなんらかの事故の可能性がありますので、応募先・問い合わせE-mailアドレスまでお問い合わせください。
(8) 応募の採択・不採択の結果については、秋季大会企画委員会および幹事会で審査の上、7月中旬ごろにご連絡する予定です。審査の上、採択されれば、報告のキャンセル・取り下げは原則としてできませんのでご注意ください。
(9) 自由論題およびテーマ別分科会で報告が採択された方には、事前(予定では10月10日(木)まで)にフルペーパーを、自由論題は70部・テーマ別分科会は100 部(日本語が望ましいが英語も可、その他の言語は不可)、開催校への送付をお願いしていますので、あらかじめご了解ください。
(10) 自由論題およびテーマ別分科会で報告された会員は、大会での報告後、フルペーパーに改善を加えて、社会政策学会誌『社会政策』に投稿されることを、幹事会と学会誌編集委員会は奨励し、期待しています。大会用フルペーパーは、その後の投稿を考慮してご執筆ください。なお、『社会政策』へ投稿する資格があるのは、会員のみです。テーマ別分科会については、学会誌での小特集に応募することも可能です。ふるってご投稿ください。
秋季大会企画委員会委員長 石井まこと
mak@oita-u.ac.jp
郵送の場合
〒870-1192大分県大分市旦野原700番 大分大学経済学部 石井まこと
(封筒に「社会政策学会大会報告応募」と明記してください)
次回秋季(127回)大会の共通論題について
2013年05月08日
4月13日に開催の共通論題の打ち合わせ会において、共通論題タイトルを「居住保障と社会政策」とすることにしました。一部修正することになりましたので、お知らせします。
秋季大会企画委員会・委員長 石井まこと
Plenary Session Abstract in English (SSSP 126th Biannual Conference)
2013年05月02日
Chair : Kimiko KIMOTO (Hitotsubashi University) and Kazue ENOKI (Hosei University)
Basic Law for a Gender-Equal Society, implemented in 1999, established the realization of a gender-equal society as “the most important issue that will determine the society of our country in the 21st century.” Today, more than a decade after the law’s implementation, its ultimate goal will be confirmed once again and the possibilities for gender equality in social policy will be explored, with a focus on labor issues. The first report discusses the disparities in the workplace and strategies to resolve them. A comprehensive problem proposal is offered for realizing the principle “equal pay for equal work” for wage disparity adjustment. The second report examines care labor as a contact point between the household and labor. In the third report, the taxation and social security systems of Japan will be observed from the perspective of the relationship between labor and the child allowance system. This report also examines how society is breaking away from the “male breadwinner” structure.
Abstract
1. Economic Gap and Equity among Employees -Aiming at a Transformation from “Japan’s 1960’s System” to a New Social System-
Koshi ENDO (Meiji University)
“Japanese employment practices” and “male bread-winner families” have been tightly bound each other in the 1960’s in Japan. This bind shall be called “Japan’s 1960’s System.” This social system has been accepted and perpetuated for a long time since then, as many consider it to be the system most fitting for the development of Japanese economy. However, this system was also characterized by economic gaps across gender lines and between regular and non-regular employees. This inequality has resulted in discrimination against female and non-regular employees.
Recently, the conditions for the existence of “Japan’s 1960’s System” have begun to disappear. But, the economic gap and discrimination described above still exists. This has become a growing problem in Japanese society.
I will overview the present situation of “Japan’s 1960’s System”. I will then argue that a return to the traditional system is not a valid solution to the present social problem, but that an effort to establish a new social system built on the job-based employment practices and the diverse family structures is a true solution.
The job evaluation system based on the pay-equity principle is a fundamental part of this true solution. I will cite where its research and development have attained feasibility and which system is the more preferable to Japanese employees between two. In addition, I will describe the great opportunity for young researchers to play an essential role in developing a true solution incorporating this new job evaluation system based on the pay-equity principle.
2. Visiblization of Care as Work in Social Policies: Issues of the Long-term Care Insurance System Uncovered through Paid Care Work Assessment
Mie MORIKAWA (National Institute of Public Health)
The ten years since the implementation of the Basic Law for a Gender-Equal Society coincide with those following the implementation of the long-term care insurance system. The long-term care insurance system came into effect in 2000 with a principle of “socialization of care” based on the intention that society as a whole would support the care work that had been placed on many women as unpaid work within families. This system has expanded rapidly as a result of 1) the sound financial foundation attained by reforming the social insurance system and 2) the introduction of a system which has enabled the provision of care services in large quantity due to quasi-marketization of care provision. The system expansion also implies progress in laborization of care work in the sense that the expansion produced a large number of care workers.
Such trends can also be interpreted as a movement of Japan’s social policies breaking away from the “male breadwinner model,” which supports the labor framework consisting of “male, productive, paid work” and “female, reproductive, unpaid work.” On the other hand, the long-term care insurance system has been facing a lack of sustainability in the aspect of reproduction of workers, which suggests that there are serious issues brought about during the process of visiblization of care provision through quasi-marketization (identification of care work as a subject of social and economical assessments).
In this presentation, using the example of home-visit care services, it will be shown that visiblization of care work through the long-term care insurance system entails serious issues. Specifically, these issues lie not only in the social and economic status of care workers such as the wage and conditions of employment but also in the normative aspect including establishing the assessment criteria care work. On that basis, it will be discussed that the care work value system imposed as the norm by the long-term insurance system is distinctive in that it relies on a double fiction of “fictitious labor” and “fictitious commodities.” Then, it will also be argued that such a care work value system itself imposes a certain limitation on the operation of the system. Finally, based on the discussions from the presentation, an outlook will be presented on 1) assessments of Japan’s future activities in the sphere of reproduction, including care work, and 2) visions of Japan’s welfare pluralism.
3. Child Allowance as the Linkage and Gender Equality
Akemi KITA (Fukui Prefectural University)
Social insurance-centered policy lacking in demogrants and “male breadwinner-centered policy” lacking in the principle of equal pay for work of equal value interact with one another. This is one of the major reasons why Child Allowance has been vulnerable and why various arguments against Child Allowance have been produced in Japan. The following were two typical views to oppose the Child Allowance Law enactment in the late 1960’s.
“What is the purpose of ……Child Allowance? If it aims at a modification of wages or means a kind of social security benefit, it is not appropriate to supply upper-income earners without income test.” “If it aims at increase in the birthrate, I won’t agree to the proposal that forces the national economy to bear the financial burden of Child Allowance not so effective for such a purpose while the Ministry of Health and Welfare overlooks “abuses” of the Eugenic Protection Act. (Juitsu KITAOKA).”
“There will be no need for introducing Child Allowance if we improve tax allowance for dependants and family allowance as a part of wages up to the level of actual living expenses.” “The cost of bringing up children should be included in wages as the reproduction cost of labor force.” (Shigeru AOKI)
In some cases, critics argue that substantial day nursery services can replace Child Allowance, or they say the priority should be given to benefits for single mothers or to measures to tackle child poverty instead of Child Allowance payable to rich two –parent families. In other cases, critics argue that employment support for young people and women is more important than Child Allowance by cash limited to childrearing family. These arguments are also influenced by the two interacted absences of demogrants and the principle of equal pay for work of equal value mentioned above. But, In reality, the deterioration of Child Allowance would accelerate the poverty of women and younger generations because these are one and indivisible phenomena.
I would like to discuss here that child Allowance is essentially not only the linkage between social insurance and public assistance but also one between minimum wage and social security benefits. The lack and institutional vulnerability of it would negatively affect the totality and consistency of social policy and would pave the way for market fundamentalism re-strengthening gender bias. These days, the reduction scheme of public assistance, which will be greater damages to families with a greater number of children, is attracting a great deal of attention. This problem is also concerned with the fact that Child Allowance does not have a proper and important place in Japanese social policy.
[Special Lecture] The participation of women in the labour market and childcare investment: views from Europe
Margarita León (Autonomous University of Barcelona)
Downloading a paper to read 
One of the most important changes that have taken place in European societies since the 1960s and 1970s has been the incorporation of women to paid employment. The industrial economy pretty much built around male workers has given way to a service economy changing jobs and also workers. These changes in employment together with changes in the role of women has brought about a wide number of tensions and conflicts in modern European societies. This presentation will firstly focus in the tensions that exist between the participation of women in paid employment and fertility looking at changing dynamics and existing tensions in both female employment and fertility. Secondly, the presentation will analyze developments in childcare provision (Early Childhood Education and Care – ECEC) within the framework of a proposed paradigmatic change of welfare states through ‘social investment’. The presentation will give an overview of the current academic and political debate around the pros and cons of expanding service provision for small children (that is, children under compulsory school age). Developments in ECEC at least at the European level have certainly been backed up by a vast amount of research that prove, albeit with different emphasis, positive links between investment in ECEC and (1) female labour force participation, (3) fertility dynamics (3) children’s opportunities in life and (4) productivity imperatives in the knowledge-based economy. Despite the fact that causal connections are very difficult to identify (Gerda & Andersson 2008), it truly exists strong empirical evidence on the connections between the labour market participation of women –specially mothers with under school age children- and availability of childcare provision and/or other family-oriented policies (Kamerman & Moss 2009; Boje & Ejnraes 2011). Family policies oriented towards female employment –such as availability of public childcare- have a positive impact on levels of female employment (Gauthier, 2007) and vice-versa. However, there are significant differences between European countries not just in levels of ECEC coverage but on aspects related to the quality of the provision. Furthermore, it is important to look at ECEC development within broader policies for the reconciliation of work and family life, mainly forms of flexible but secured employment and parental leave schemes. The presentation will finally give an overview of the present challenges and dilemmas that European countries face nowadays with expanding ECEC services in the context of strong austerity social and economic programmes that the EU is imposing on member states as a response to the economic crisis.
« 次のページ
前の記事 »