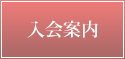秋季大会の開催と、台風19号の接近の影響について
2014年10月10日
台風19号の沖縄・西日本接近による天候悪化が予想されていることから、秋季大会は予定どおり開催されるのかというお問い合わせをいただいています。
大会は、予定どおり開催いたしますが、天候の急変により、大会2日目のスケジュール変更等を行う場合は、大会会場でお知らせするほか、学会ホームページに情報を掲載いたします。
https://jasps.org/
大会参加にあたっては、台風の進路や天候の変化に関する情報をご確認いただき、往路・復路の安全の確保にご留意いただきますようお願いいたします。
なお、万が一、大会での報告を予定されている方で、台風の影響で大会参加が不可能になった場合は、何らかの救済措置を検討いたしますので、学会本部(代表幹事)までご一報いただきますようお願いいたします。
第129回大会のフルペーパーの電子配布について
2014年10月01日
大会終了後2週間が経ちましたので、ファイルを削除しました。
部会名称のリンクをクリックした先のページからダウンロードしてください。
・共通論題と書評分科会は電子ファイルの事前配布はありません。
・公開は2014年10月26日(日)までです。
・第129回大会では会場にて公衆無線LANアクセスにアクセスできます(2014/09/06)。
・ユーザー名(ID)とパスワードの使い方などの不明な事柄についてはこちらの説明を参照して下さい。
注1.報告者の名前の右に記した「 <報告ファイル> 」という文字がファイルへのリンクです。
注2.「 当日配布 」とあるのは、企画委員会が指定した期日までにフルペーパーが提出されなかった報告です。当日、報告者により、印刷物が指定部数持ち込まれます。
☆ 社会政策学会のサイトにつながらないときはミラーサイト(予備のサイト)からダウンロードしてください。ダウンロードできるファイルは同じです → ミラーサイトへのリンクはこちら(首都大学東京内)
129回大会・大会2日目・フルペーパー(午前の部 09:30~11:30)
2014年10月01日
大会終了後2週間が経ちましたので、ファイルを削除しました。
9:30~11:30 12:50~14:50 15:00~17:00
(作業中、参加者用パスワードは使えません)
お断り:書評分科会は電子ファイルの事前配布はありませんので掲載しておりません。
<自由論題・第1 職業訓練>
座 長:橋場俊展(名城大学)
1.公共職業訓練実施の在り方―自己啓発の実施・職場定着・賃金に対する効果に注目する―
陸 光杰(大阪市立大学・院生) <報告ファイル>
2.就業構造基本統計調査等による公共職業能力開発の位置づけ
大矢奈美(青森公立大学) <報告ファイル>
<自由論題・第2 サービス供給主体>
座 長:高野 剛(立命館大学)
1.民間賃貸住宅の家主とは誰か―公的建設費助成の諸前提として―
佐藤和宏(東京大学・院生) <報告ファイル>
2.非営利・営利主体の訪問介護事業所の行動比較分析
金谷信子(広島市立大学) 当日配布
<テーマ別分科会・第1>
竹中理論の諸相(第二回):女性労働運動と家族
座 長: 原 伸子(法政大学)
コーディネーター:北 明美(福井県立大学)
1.関西における女性労働運動と竹中理論
伍賀偕子(元大阪総評・元関西女の労働問題研究会) <報告ファイル>
2.新自由主義時代の労働・家族分析の課題
蓑輪明子(東京慈恵会医科大学) <報告ファイル>
129回大会・大会2日目・フルペーパー(午後の部 12:50~14:50)
2014年10月01日
大会終了後2週間が経ちましたので、ファイルを削除しました。
9:30~11:30 12:50~14:50 15:00~17:00
(作業中、参加者用パスワードは使えません)
<自由論題・第3 労使関係>
座 長:戸室健作(山形大学)
1.日本的雇用システムと同一労働同一賃金
岩田克彦(国立教育政策研究所) 当日配布
2.米国の労使関係システムの再定義と日本への示唆
山崎 憲(労働政策研究・研修機構) <報告ファイル>
3.19世紀末から20世紀初頭にかけてのイギリスにおける外国人移民と労働規制:ウェッブ夫妻の苦汗労働研究を参考にして
齋藤翔太朗(東京大学・院生) <報告ファイル>
<自由論題・第4 貧困>
座 長:藤原千沙(法政大学)
1.社会的孤立者数の推計と孤立の要因分析
阿部 彩(国立社会保障・人口問題研究所) 当日配布
2.中高年の失業と生活困窮の実情についての分析
西垣千春(神戸学院大学)・田宮遊子(神戸学院大学) 当日配布
3.誰が生活保護をバッシングしているのか?-インターネット調査の結果を手がかりに-
山田壮志郎(日本福祉大学) <報告ファイル>
<自由論題・第5 高齢者福祉>
座 長:田中裕美子(下関市立大学)
1.地域包括ケアの推進と家族介護支援策の再検討―東京都区市町村の取り組みに焦点をあてて―
菊池いづみ(日本社会事業大学) <報告ファイル>
2.高齢者生活協同組合による社会サービス供給の事業展開
熊倉ゆりえ(明治大学) 当日配布
3.ホームヘルパーによる高齢者の看取り対応の実態と課題―訪問介護現場における聞き取り調査結果からの考察―
高橋幸裕(帝塚山大学) <報告ファイル>
<自由論題・第6 社会政策の思想>
座 長:杉田菜穂(大阪市立大学)
1.イギリス福祉国家再編におけるキャメロン政権の「大きな社会」構想の経済思想
平方裕久(九州産業大学) 当日配布
2.優生学と日本の社会政策
矢野 聡(日本大学) 当日配布
3.「脱家族化」からみるスウェーデンの福祉・教育予算編成方法
大岡頼光(中京大学) <報告ファイル>
<テーマ別分科会・第2>
東アジアにおける外国人労働者、移民と多文化主義 〔日本・東アジア部会〕
座 長・コーディネーター:李 蓮花(静岡大学)
予定討論者: 武川正吾(東京大学)
1.東アジア地域経済統合下の外国人政策
井口 泰(関西学院大学) 当日配布
2.東南アジアにおける家事介護労働市場の現状―日本への影響―
山田健司(京都女子大学) <報告ファイル>
3.台湾における「新移民」と多文化主義:結婚移住者支援組織と学校教育現場における調査事例から
金戸幸子(藤女子大学) 当日配布
<テーマ別分科会・第3>
就労可能な生活困窮者への生活保障と就労支援:日独比較の視点から
座 長・コーディネーター:布川日佐史(法政大学)
予定討論者: 吉永 純(花園大学)
1.失業者生活支援施策の中の生活保護法の役割
木下秀雄(大阪市立大学) 当日配布
2.生活困窮者自立支援法と生活保護改革
布川日佐史(法政大学) 当日配布
3.生活保護法上の自立の助長をめぐる法的課題
前田雅子(関西学院大学) 当日配布
<テーマ別分科会・第4>
労働・職業教育の新地平 〔労働史部会〕
座 長・コーディネーター:石塚史樹(西南学院大学)
予定討論者: 枡田大知彦(専修大学)
1.日本における労働経済教育の過去と現在: 教科書サーベイによるアプローチ
伊佐勝秀(西南学院大学) 当日配布
2.実務家による労働教育の現状と課題
水野勝康(愛知県社会保険労務士会) <報告ファイル>
3.フランスにおける職業教育の諸相
五十畑浩平(香川大学) 当日配布
129回大会・大会2日目・フルペーパー(午後の部 15:00~17:00)
2014年10月01日
大会終了後2週間が経ちましたので、ファイルを削除しました。
9:30~11:30 12:50~14:50 15:00~17:00
(作業中、参加者用パスワードは使えません)
<自由論題・第7 移民労働>
座 長:久本貴志(福岡教育大学)
1.先進国における外国人家事労働者の増加要因の比較分析
伊藤善典(一橋大学) <報告ファイル>
2.非可視化する外国人介護労働者―イタリアの移民政策と地方政策―
宮崎理枝(大月短期大学) <報告ファイル>
3.国境を越える人の移動と社会給付の受給
松本勝明(厚生労働省) <報告ファイル>
<自由論題・第8 子どもへの支援>
座 長:吉中季子(名寄市立大学)
1.生活保護世帯への学習支援に関する研究
田中聡子(県立広島大学) <報告ファイル>
2.児童養護施設の進学、就職支援効果に関する量的分析
森山智彦(下関市立大学)・浦坂純子(同志社大学) <報告ファイル>
<自由論題・第9 医療>
座 長:森 周子(高崎経済大学)
1.1980年代以降の医療機能の分化・連携政策の展開―社会的学習論の視座から―
竜 聖人(筑波大学・院生) <報告ファイル>
2.フランス19世紀における共済組合と医療
小西洋平(京都大学・院生) 当日配布
<自由論題・第10 社会保険>
座 長:菊地英明(武蔵大学)
1.福祉国家論から見た厚生年金基金
福田 順(同志社大学) <報告ファイル>
2.対外経済政策としての社会保障―韓国公的年金の新たな役割―
井上 睦(一橋大学) <報告ファイル>
3.労働災害と社会保障―石綿健康被害救済法における労災保険の補完的政策の意義について―
南 慎二郎(立命館大学) <報告ファイル>
<テーマ別分科会・第5>
韓国の女性労働の諸相:「インフォーマリティ」の視点から 〔ジェンダー部会〕
座 長・コーディネーター:服部良子(大阪市立大学)
予定討論者: 横田伸子(山口大学)
1.ジェンダーの視点から見た韓国における「インフォーマル」な就業の実態と労働市場構造―1990年代以降を中心に―
イ・ジュヒ(梨花女子大学校) 当日配布
2.韓国における女性自営業者層形成の歴史的考察―釜山地域の実態調査から―
李 明輝(梨花女子大学校) 当日配布
<テーマ別分科会・第6>
生活困窮者支援事業の現状と課題 〔社会的排除/包摂部会〕
座 長: 櫻井純理(立命館大学)
コーディネーター:福原宏幸(大阪市立大学)
1.生活困窮者支援の制度的枠組みと課題―アクティベーション政策の視点から―
福原宏幸(大阪市立大学) 当日配布
2.生活困窮者支援事業実施自治体の現状と課題―地域社会資源の育成と活用の視点から―
五石敬路(大阪市立大学) 当日配布
3.生活困窮者支援事業の受託民間団体の現状と課題―就労準備と中間的就労を担う社会的企業―
藤井敦史(立教大学) 当日配布
4.生活困窮者支援における相談支援のあり方と課題―伴走型支援のスキームと機能―
垣田裕介(大分大学) 当日配布
5.社会的企業による生活困窮者労働支援の現状と課題―当事者性を重視した労働支援のあり方の検証―
大高研道(聖学院大学) 当日配布
<テーマ別分科会・第7>
完全雇用の限界と日欧における生活保障の新たな動向 〔雇用・社会保障の連携部会〕
座 長: 石川公彦(明治大学)
コーディネーター:高田一夫(一橋大学)
1.オランダにおけるフレキシキュリティと長期失業者にかかわる現状と対応策
久保隆光(明治大学) 当日配布
2.貧困理論の再検討―相対的貧困から社会的排除へ―
志賀信夫(一橋大学・院生) 当日配布
3.日本における「第二のセーフティネット」の現状と課題
佐々木貴雄(東京福祉大学) 当日配布
LERA2015年大会報告者募集のお知らせ
2014年09月25日
LERA(Labor and Employment Relations Association) 67th Annual Meeting(ペンシルバニア州ピッツバーグで2015年5月28日~31日開催)では、社会政策学会とLERAがジョイントセッションの企画 をしています。テーマは日本とアメリカでの不安定雇用労働者の組織化で、日本側とアメリカ側からそれぞれ2人が報告し、コ メンテータが日米の比較について討論する予定です。
国際交流委員会は、ジョイントセッションでの報告者を募集いたします。報告を希望される方は、200 words程度の英文の報告要旨(abstract)を作成し、10月17日(金)までに国際交流委員会副委員長・鈴木玲までメールで送付を願います。詳しくは下記の文書をご覧ください。
LERA_presenter 
NL No. 80の発刊について
2014年09月07日
ニューズレターNo.80ができあがりました。会員の皆様のおてもとに郵送されますまで、しばらくお待ちください。
NL No. 80 
第20回(2013年)学会賞選考委員会報告
2014年09月07日
【学術賞】
伊藤セツ
『クラーラ・ツェトキーン ―ジェンダー平等と反戦の生涯―』
(御茶の水書房)
【奨励賞】
該当なし
学会賞選考委員会
猪飼周平、禹宗杬(委員長)、清水耕一、宮坂順子、横田伸子
1.選考経過
2013年10月の幹事会で上記5名の選考委員が委嘱された。
今回からは、日本語だけでなく英語による著書も選考の対象とすることになり、学会ホームページとニューズレターを通して自薦・他薦を募ったが、残念ながら対象作は得られなかった。次回からは多数の推薦があることを期待する次第である。一方、通常の日本語著書に関しては、ホームページとニューズレターにおいて呼びかけたところ、1点の他薦を得ることができた。
なお、2013年12月末にワールドプランニングから会員名簿を取り寄せ、大型書店のデータベースを用いて2013年1月から12月までに刊行された会員の著書を検索し、そこから会員暦3年以上会員の単著64冊を選び、そのリストを各委員に送付した。
第1回選考委員会を2014年1月25日、埼玉大学東京ステーションカレッジにて開催した。最初に、学会の表彰規程に照らして選考基準を確認するとともに、教科書類は除外すること、当分共著も除外することなどに合意した。
この合意にしたがい、上記64冊の現物確認のうえ、明らかに一般向けで学術書でないものなど28冊を対象外とし、残りの36冊を1次審査の対象にすることとした。
これら選考対象の著書をそれぞれ2名の委員に担当を割り振り、次回の選考委員会までに各自候補作を選び、それを持ち寄ることとした。
第2回選考委員会を4月5日、埼玉大学東京ステーションカレッジにて開催した。1次審査の対象となった36冊について、担当の2名の審査所見をもとに1冊ずつ審査を行い、学術賞および奨励賞の最終選考に進むことのできる作品として、計6冊を選考した。
そして、これら審査対象の著作に関し、全員が精査のうえ、各自それぞれの著作についてコメントを作成し、次回の学術賞および奨励賞の決定に臨むこととした。
第3回選考委員会を5月10日、埼玉大学東京ステーションカレッジにて開催した。最終選考の対象となった6冊について、1冊ずつ慎重に審査を行い、学術賞および奨励賞の対象について検討した結果、学術賞として上記の1冊を選定し、奨励賞については該当なしの結論を得るにいたった。
2.選考理由
伊藤セツ 『クラーラ・ツェトキーン ―ジェンダー平等と反戦の生涯―』を学術賞として選定した理由は、次のとおりである。
本書は、マルクス主義女性解放論の主唱者の一人であるクラーラ・ツェトキーンの評伝である。
著者によれば、本書の目的は、第一に、クラーラ・ツェトキーンという人物の実像にせまることであり、第二に、「クラーラのかかわった女性運動に関する発言や著作、行動や生き方が、世界のジェンダー平等の運動や現在の日本の『男女共同参画』の実現に連なるもの、寄与するものは何であったかを考察する」ことである。
本書は、貴重な一次資料、すなわち手紙と演説・論考などクラーラ自身が残したもの、および彼女の言動を叙述した議事録や議事などのほか、多くの資料に丹念に当たり、「クラーラ・ツェトキーンという人物の実像」を復元することに成功している。
それは、一つには、クラーラ・ツェトキーンの理論・政策についてである。彼女の理論・政策を階級一元論的なものとして片づける傾向のあるなか、著者は、「性の問題」と「階級・階層の問題」という両側面から女性の具体的要求を把握し、それを運動の政策に結びつけることこそ、女性問題に対するクラーラの理論・政策の特徴であると、捉え直しているのである。復元は、二つには、クラーラ・ツェトキーンの思想形成の全体像についてである。著者は、クラーラの運動家としての側面だけでなく、少女時代から晩年にいたるまで彼女が経験・思索したことを、私的葛藤をも含めて抉り出すことを通して、一人の歴史的人物のリアリティーに迫っているのである。
本書は、「今日の現実に連なるもの、寄与するもの」に関しても、①女性運動に対する社会主義者の男性の態度の問題、②女性解放の土台としての女性の経済的自立の重視の問題、③そのためにこそ必要な女性労働者保護の問題、④女性運動における家庭的なことをどうとらえるかの問題、⑤女性を社会変革的運動に引き入れるための特別な配慮の問題、⑥現代の国際的女性運動とのつながり、とまとめており、頷ける。
こうして本書は、クラーラ・ツェトキーンの思想とその軌跡を仔細に描写しているが、クラーラという人物の実像をこれほどまでの精緻さをもって跡付けた研究は、国内外を通しても見つけがたく、その業績は高く評価しなければならない。なお、本書は、著者の50年にわたるライフワークの成果であり、一つの研究対象に対してこれほど掘り下げ続けられる研究姿勢も大いに見習うべきである。
ただし、後学として一点だけ求めるのであれば、それは、クラーラ・ツェトキーンの今日に対する示唆についてである。
うえで取り上げた六つの事項は、「クラーラがおかれたその時代的場所的背景のなか」の女性運動と、日本の現実の女性運動との間に、ある種の普遍的な問題が横たわっていることとしては理解できる。ただし、クラーラの置かれた背景と日本の現実との間に、著者の強調する、女性運動の「具体的要求」においては、どのような違いがみられるのであろうか。そして、マルクス主義女性解放論は、いまを生きているわれわれに対して、どのような功罪を残しているのであろうか。著者は、謙虚にしてこれらについて多くを語らないが、後学としてはさらなる成果を期待してやまない次第である。
以下、受賞作の選定にはいたらなかったが、学術賞ならびに奨励賞の最終候補となった著作についても若干講評を記すことにする。
まず、学術賞の最終候補となった、大沢真理 『生活保障のガバナンス ―ジェンダーとお金の流れで読み解く―』(有斐閣)についてである。
本書は、国際比較をふまえ、日本の生活保障システムの特徴を抉り出すとともに、そのガバナンスの推移を1980年代以前から今日にいたるまで跡付け、日本の生活保障システムの問題点と課題を明らかにしたものである。
分析の結果、日本の生活保障システムは、諸外国にみられないほど強固な「男性稼ぎ主型」であり、したがって貧困は、夫婦共稼ぎ世帯や有業のひとり親世帯などによく見られ、とくに女性にワーキング・プアが多いことが導きだされた。
日本の生活保障システムは、高い相対的貧困率、低い貧困削減率、高い地域間所得格差をもたらし、むしろ社会的排除の装置となり、逆機能していることが示されたのである。
本書が、エスピン=アンデルセンをはじめとした先行研究の丹念な検討に基づき、政府や企業、家族の目的合理的な介入(ガバニング)のみならず、生活保障を意図しない官民の相互作用をも含めて、それらの効果の総体をみる観点から、「福祉国家」の手段と考えられていないような制度や政策が、福祉国家の機能を代替する側面にも配慮するなど、より広いフレームワークの構築に積極的に取り組んでいることは高く評価できる。
なお、OECDのデータを活用して国際比較を行いつつ、日本のガバナンスの特徴を歴史に沿って丹念に検討し、今後に向けての示唆を引き出していることも、大いに評価しなければならない。
ただし、課題もあるように思われる。その一つは、「財・サービスを生産する4つの関係」をもって、従来のフレームワークに代えようとしていることである。「商品―商品」「商品―非商品」「非商品―商品」「非商品―非商品」という4つの関係自体は理解できるものの、これをもって各国の生活保障システムを類型化するところまではいたっておらず、なお日本の場合も、この4つの関係に即した分析が、今後に向けての示唆とどのように関係するのか、必ずしも明確でないことが惜しまれる。
ほかに、本書の採用する「逆システム学」が、はたして新たな知見を導出する理論枠組みとして機能し得るかや、労働組合について本書でほとんどふれられていないこと、そして、本書が全体として叙述的(descriptive)であって分析的(analytic)でないことも問題提起された。
次に、奨励賞の候補作となった、伊藤大一 『非正規雇用と労働運動 ―若年労働者の主体と抵抗―』(法律文化社)についてである。
本書は、7年にわたる実態調査に基づき、トヨタ自動車の1次サプライヤーJ社の完全子会社であるアイズミテックの請負労働者たちが、労働組合を結成して偽装請負を告発するとともに、ストライキを実施するなどして正社員化を獲得した経緯を明らかにしたものである。
本書が示している、請負労働者の労働過程、正規従業員と請負労働者が混在する労働編成、高技能の請負労働者が中心であるために彼らを正規従業員で代替できなかった特殊事情、請負労働者の労働条件や請負労働者に対する労務管理および偽装請負の実態、請負労働者組合を結成する過程と少数派正社員労働組合の支援、地域労働市場の特徴と請負労働者の社会関係資本および生活・文化などは、それ自体として貴重な学術的貢献であり、興味深い。
なお、「若年労働者の主体について考えてみたい」という著者の意図も共感できるものであり、長い年月をかけて調査を続けたことも高く評価すべきである。
ただし、問題がないわけではない。第一に、事実認識において正しくないところが散見される。たとえば、「この『二重雇用形態』、『請負と雇用の未分離状態』から戦時体制、戦後の高度成長を経て、直接雇用中心の雇用労働者が主流となっていく」(p.24)というところや、25ページ以下のトヨタの「組請負」に関する記述などがそれである。第二に、調査においてより綿密さが求められる。たとえば、アイズミテックが請負という形態を選択した理由や、偽装請負発覚後の契約社員化・正社員化への政策変更について、会社および多数派正社員労組の見解を調査できていないことは、惜しまれるところである。
なお、調査結果をもとに行論する場合、どの一次資料のどの部分を用いたのかが明確でなく、どこまでがインタビューから導き出された結論なのかが判然としないことも問題と言わざるを得ない。今後のさらなる研究成果を期待したい。
最後に、選考過程において感じられたことを少し述べさせていただきたい。今度の選考においても対象となった著作はバラエティーに富み、意欲的な作品も少なからずみられた。ただし、全般的な印象としては、その意欲とは裏腹に、あるいはその意欲のせいで、刊行が急がれているような感じを拭えなかった。もともと研究成果を競い合い、それを世に問うのは、われわれ研究を目指す者たちの本分といえよう。しかし、刊行を急ぐあまり、新たな理論の探求や精緻な実証の追究が多少なりともおろそかになることがあれば、それは慎むべきといわなければならない。少しは余裕を持って、研究と刊行に臨む必要があるように思う次第である。
学会賞選考委員会委員長 禹宗杬
129回大会での大会会場における無線LANの利用について
2014年09月06日
第129回大会では、岡山大学内で岡山県の公衆無線LANを無料で利用できます。詳細は以下のURLの説明をご覧ください。
http://www.citm.okayama-u.ac.jp/citm/service/okayama_mobilespot.html
利用をご希望になる方は、ノートパソコンなど、ご自身の端末を持参してください。なお、学会では、個々の端末における設定など、サポートはできませんので、その点はご了解ください。
以上、どうぞよろしくお願いします。
第129回大会プログラム(PDF)
2014年08月27日
第129回大会プログラムができあがりました。まもなく会員の皆さんのお手元に届くと思います。暫くお待ちください。下記はPDFファイルです。ご活用ください。
第129回大会プログラム 
お断り 1 : こちらのファイルからは、大会報告フルペーパーのダウンロードに必要となるIDとパスワードが書かれたページは削除してあります。IDとパスワードについては冊子体をご利用下さい。
お断り 2 : 大会プログラムの送付と、ニューズレターの送付タイミングが重なることから、9月5日発刊予定のニューズレターから、ニューズレターには大会プログラムを掲載しないことになりました。あしからずご了承ください。
« 次のページ
前の記事 »