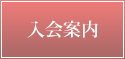第136回大会・大会1日目・フルペーパー(午後の部 12:45~14:45)
2018年05月16日
*下線は登壇者
<テーマ別分科会・第2> 【1号館304講義室】
雇用関係によらない雇用類似の働き方は柔軟な働き方か 〔非定型労働部会〕
座 長:伊藤大一(大阪経済大学)
コーディネーター:渡邊幸良(同朋大学)
1.在宅ワークで働く母子家庭の母親と障害者の実態―面接聞き取り調査から
髙野 剛(立命館大学) <報告ファイル>
2.個人請負就労者にはどのような保護政策が必要か―建設職種から考える
柴田徹平(岩手県立大学) <報告ファイル>
3.シェアリングエコノミーと労働者の権利
川上資人(東京共同法律事務所・弁護士) <当日配布>
<自由論題・第3 労使関係・労務管理> 【1号館205講義室】
座 長:石井まこと(大分大学)
1.終末期における全百連の内部対立に関する一考察
本田一成(國學院大學) <報告ファイル>
2.中国における「蟻族」現象に関する一考察―中小民営企業の人事・労務実態を中心に―
李 暁静(明治大学・院生) <報告ファイル>
3.国立病院・療養所労組と特殊勤務加俸問題
西村 健(松山大学) <報告ファイル>
<自由論題・第4 貧困と社会保障> 【1号館203講義室】
座 長:大塩まゆみ(龍谷大学)
1.在宅医療需要の推計
齋藤立滋(大阪産業大学) <報告ファイル>
2.生活保護バッシングをするのは誰か:一般市民の意識調査を用いた実証分析
梶原豪人(首都大学東京・院生)、阿部 彩(首都大学東京)、東 悠介(日本学術振興会・東京大学)、石井東太(首都大学東京・院生)、谷川文菜(首都大学東京・院生)、松村智史(首都大学東京・院生)<報告ファイル>
3.不登校リスクと子どもの生活の質について
内藤朋枝(政策研究大学院大学・院生) <報告ファイル>
<博士論文報告会・第1> 【1号館302講義室】
座 長:鬼丸朋子(中央大学)
1.少子高齢化社会における技術伝承と人材育成―建設技術者の検証―
山﨑雅夫(法政大学)
2.外資系企業の経営戦略と雇用・処遇のマネジメント―生命保険会社の事例研究を中心に―
垣堺 淳(ジブラルタ生命保険株式会社)
3.非正規雇用化が進行する認可保育所における職場集団の構造と機能
小尾晴美(名寄市立大学)
4.港湾産業における労使関係の展開と労働組合運動
鈴木 力(一橋大学)
5.日経連の賃金政策―定期昇給を中心として―
田中恒行((一社)東京経営者協会)
※博士論文報告会は事前のペーパー配布はありません。
第136回大会・大会1日目・フルペーパー(午後の部 14:50~16:50)
2018年05月16日
<テーマ別分科会・第3>【1号館205講義室】
大学における労使関係の現状 〔労働組合部会〕
座 長・コーディネーター:兵頭淳史(専修大学)
1.公立大学法人の労使関係―首都大学東京の事例など―
小林喜平(首都大学東京) <当日配布>
2.私立大学における労使関係の今日的特質―A学院大学における一時金削減をめぐる労使紛争の分析を通じて―
白井邦彦(青山学院大学) <報告ファイル>
<国際交流分科会JASPS-LERA Joint Session> 【1号館304講義室】
Rise of New Ways of Utilizing Labor without Employment Relationship and the Limits of Current Form of Labor Laws
Chair: Akira Suzuki (Hosei University)
Discussant: Charles Weathers (Osaka City University)
1. The Withering Away of the Traditional Employment Relationship: Reality and Implication for Labor Law
Janice R. Bellace (Wharton School – University of Pennsylvania)<Download 1><Download 2>
2.The current state of dependent contractors and policy issues in the construction industry in Japan
Teppei Shibata (Iwate Prefectural University, Faculty of Social Welfare)<Download >
<自由論題・第5 福祉国家とジェンダー> 【1号館203講義室】
座 長:朱 珉(千葉商科大学)
1.中国における女性のワークライフバランス―聞取り調査を基に
劉 佳(東京大学・院生) <報告ファイル>
2.協働の統治モード
高橋 聡(岩手県立大学) <報告ファイル>
3.再生産レジームにおける政策方向の再編
金 志勲(東京大学・院生) <報告ファイル>
<博士論文報告会・第2> 【1号館302講義室】
座 長:畠中 亨(帝京平成大学)
1.ドイツ社会国家における「新自由主義」の諸相―第二次赤緑連立政権における財政再編を事例とした考察―
福田直人(東京大学)
2.児童扶養手当制度に関する研究―国会審議にみる支給金額の形成過程―
堺 恵(龍谷大学)
3.日本における難病政策の形成と変容の研究:疾患名モデルによる公費医療のメカニズム
渡部沙織(日本学術振興会・明治学院大学)
※博士論文報告会は事前のペーパー配布はありません。
社会政策関連学会協議会フォーラム(2018年6月30日)
2018年04月25日
社会政策学会会員各位
本学会が加盟する社会政策関連学会協議会主催の若手研究者支援フォーラム「初めての査読論文―経験者が語る投稿から掲載まで」が6月30日、明治大学にて開催されます。
参加費無料、参加申込不要です。
このフォーラムでは、学会誌に論文を投稿して採択された若手研究者に、投稿論文を執筆する際に留意したことや査読意見をどのように受け止め対応したかなど、投稿から掲載までの経験についてお話しいただきます。また、投稿を受け付ける編集委員会から、査読者は何を審査しているのか、査読論文に求められる点をお話しいただきます。
本学会を含め、4つの関連学会からご登壇いただきます。
会員の皆さまにおかれましては奮ってご参加ください。
イベントチラシ 
社会政策学会幹事・社会政策関連学会協議会協議員 阿部誠・藤原千沙
第136回(2018年度春季)大会での総会議題(会則第24条改正)の追加
2018年04月23日
第136回大会(於:埼玉大学)における総会(5月26日)議題に、会則第24条改正案を追加します。改正案の内容と理由については、会員一斉メールを参照ください。
代表幹事 遠藤公嗣
第136回(2018年度春季)大会プログラム
2018年04月19日
第136回(2018年度春季)大会プログラムについて、冊子体はすでに会員の皆さんにお届けしております。下記は、ホームページ掲載版のPDFファイルです。ご活用ください。
第136回大会プログラム(確定版) 
なお、こちらのファイルでは、大会報告フルペーパーのダウンロードに必要となるIDとパスワードの書かれたページを削除しております。IDとパスワードについては、冊子体のプログラムをご利用ください。
【第136回大会プログラムの変更】
○討論者変更
・国際交流分科会 中国における「社会福祉」と家族政策
討論者1:所道彦(大阪市立大学)→森川美絵(津田塾大学)
○辞退
・博士論文報告会第2部 相藤巨→辞退、報告者順次繰り上げ
*博士論文報告会は第1部、第2部を連続して行いますのでご注意ください
JASPS Bulletinの第1号を刊行
2018年04月06日
このたび、JASPS Bulletin(本学会の英文ニューズレター・電子版のみ)の第1号が刊行の運びとなりましたので、PDFファイルを掲載いたしました。
JASPS_Bulletin No. 1 (March 2018)
このBulletinは、重点事業推進積立金に関する内規に基づく事業として実施するもので、年2回の刊行を予定しております。
このBulletinの刊行については、本学会サイトのリンク集に掲載されている海外の研究機関や学会、及び本学会と交流のある海外の研究者には、電子メイルでご案内をいたしますが、会員のみなさまにおかれましても、海外のお知り合いの研究者にお知らせいただければ幸いです。
「重点事業」担当 平岡公一
社会政策学会の電子版学会誌のJ-STAGEへの移行完了のお知らせ
2018年04月04日
社会政策学会会員各位
社会政策学会本部事務局 塚原康博
社会政策学会の電子版学会誌は、NII-ELSを通じて公開してきましたが、NII-ELSのサービスの終了にともない、J-STAGEへの移行を進めてきました。このたび、4月1日をもって、移行作業が完了しましたので、お知らせします。
J-STAGEを通じて公開されるのは、現学会誌『社会政策』、および3つの旧学会誌『社会政策学会誌』『社会政策叢書』『社會政策学會年報』です。無料で閲覧できますので、ぜひご覧ください。なお、『社会政策』については、刊行後2年を経過したものに限ります。また、『社會政策学會年報』の11~15巻については、未登載・未公開ですが、今後、登載・公開作業を進めていく予定です。
ニューズレター2016-2018年期7号(通巻94号)を掲載
2018年03月28日
ニューズレター2016-2018年期7号(通巻94号)について、PDFファイルを掲載しました。会員の皆さんには、すでに冊子体をお届けしております。
No. 94 (2018. 3. 23)
第137回(2018年度秋季)大会自由論題報告、テーマ別分科会の募集について
2018年02月28日
2018年2月28日
秋季大会企画委員会委員長 熊沢 透
社会政策学会第137回大会は、2018年 9月15日(土) と9月16日(日)に北海学園大学で開催されます。秋季大会企画委員会では、同大会の自由論題報告とテーマ別分科会企画の申請を募集いたします。申請をご希望の方は、下記の要領でご応募ください。また、報告にあたっては事前にフルペーパーの電子ファイルをご提出いただくことになっております。詳細に関しては、採択決定後に、分科会責任者や報告者の方々にご連絡申し上げます。なお、書評分科会、自由論題およびテーマ別分科会は9月15日(土)に、共通論題は9月16日(日)に行われます。
(1) 自由論題で報告を希望される会員は、学会のホームページからダウンロードした応募用紙に、報告タイトル(日本語、英語)、所属機関とポジション(日本語、英語)、氏名(ふりがな、 英語)、連絡先(住所、電話、Fax、E-mailアドレス)、400字程度の邦文報告要旨、英文アブストラクト、専門分野別コード (1.労使関係・労働経済、2.社会保障・社会福祉、3.労働史・ 労働運動史、4.ジェンダー・女性、5 生活・家族、6.その他)等の必要事項を記入のうえ、添付ファイルとして下記のE‐mail アドレスにご応募ください。
自由論題報告応募・問い合わせ先 jasps_autumn_free@googlegroups.com
担当委員:浅野和也(愛知東邦大学)、金井 郁(埼玉大学)、久本貴志(福岡教育大学)
応募様式はこちらからダウンロードしてください → 137freeapl.doc(ワードファイル)
また、論文・報告書・他の学会報告等のかたちで既発表の内容については報告できません。応募の段階で判明した場合は不採択といたしますのでご注意ください。
自由論題に応募資格があるのは、会員で、今年度分までの会費を納入されている方です。当日は、報告25分、質疑10分となります。
(2) テーマ別分科会の企画を希望する会員は、学会のホームページからダウンロードした応募用紙に、分科会タイトル(日本語、英語)、分科会設定の趣旨(日本語400字程度、非会員を報告者に招聘するときは、招聘しなければならない理由を記入)と英文アブストラクト、座長・コーディネーターの氏名 (ふりがな、英語)、所属機関とポジション(日本語、英語)、連絡先(住所、電話、Fax、E‐mailアドレス)、報告者の氏名(ふりがな、英語)、所属機関とポジション(日本語、英語)、E‐mailアドレス、各報告の邦文報告要旨(400字程度)と英文アブストラクト、予定討論者の氏名(ふりがな、英語)、所属機関とポジション(日本語、英語)等必要事項を記載のうえ、添付ファイルとして下記のE‐mailアドレスにご応募ください。なお、テーマ別分科会の企画に応募資格があるのは、会員のみです。
テーマ別分科会報告応募・問い合わせ先 jasps_autumn_thema@googlegroups.com
担当委員:森 周子(高崎経済大学)
応募様式はこちらからダウンロードしてください → 137themeapl.doc (ワードファイル)
以下は、自由論題とテーマ別分科会の応募に共通の注意事項です。
(3) 応募は、原則として、学会ホームページからダウンロードした応募用紙に必要事項を記入し、添付ファイルとして、上記のE‐mailアドレスにお送りいただくことになっています。なお、この方法による提出が難しい方は、秋季大会企画委員長までご相談ください。
(4) 応募用紙の「報告要旨」及び「分科会設定の趣旨」の「400字程度」との字数をお守りください。記入の不完全なもの、字数の著しく過剰なものや過少なものは、応募を不採択とさせていただくことがあります。
(5) 自由論題・テーマ別分科会の「報告要旨」及び「分科会設定の趣旨」のいずれについても、英文のアブストラクトを提出していただくことになっておりますので、ご注意下さい。英文アブストラクトには語数の基準は設けませんが、邦文の「報告要旨」や「分科会設定の趣旨」と同内容となるようにしてください。また、学会では英文の校閲は行いませんので、英文については、原則としてネイティブ・スピーカーによる校閲(機械翻訳ソフト利用は不可)を受けた上で、誤りや不適切な表現がないものを提出してください。英文アブストラクトは、学会の英文ホームページと英語版News Letterで公開されます。
(6) 応募にあたっては、応募時点の所属機関とポジションをご記入ください。大会プログラムには、原則として所属機関のみを表記しますが、院生の場合は所属機関とポジション(院生)を表記します。大会当日までに所属が変更となる方は、報告時のフルペーパーに新しい所属機関などを各自がお書きくださることで、変更にご対応ください。
(7) 応募期間は、2018年4月13日(金)から5月16日(水)です。締め切りは厳守です。その後の応募は不採択とさせていただきます。
(8) 応募された方に対しては、遅くとも5月19日(土)までに応募用紙受領の連絡を行います。この時までに連絡のない場合はなんらかの事故の可能性がありますので、問い合わせE-mail アドレス(あるいは下記の秋季大会企画委員長宛)にお問い合わせください。
(9) 応募の採択と不採択の結果については、秋季大会企画委員会および幹事会で審査の上、5月末にご連絡する予定です。
(10) 第128 回大会からフルペーパーは電子化されました。その目的は、フルペーパーの準備(大量印刷・送付)を行う報告者とフルペーパー管理(大量保管・移動、締切後や当日の対応、処分等)を行う開催校、双方の負担軽減です。期日までに提出できず、フルペーパーの電子化ができなかった場合には、会場で十分な議論ができないだけでなく、提出期限を守られた報告者との間で不公平が生じます。フルペーパーが用意されることで報告が成立するという点をご理解いただき、採択された場合は期日までにフルペーパーを提出されるようお願いします。
特にテーマ別分科会の申し込みにあたってコーディネーターの方は、必ずすべての報告者に、フルペーパーの提出の義務と締め切り日について説明し、了解を得ておいてください。「すべての報告者」には、分科会が招聘する非会員の方、実務家の方も含まれますので、ご注意ください。なお、フルペーパーとは学会報告の内容を学会誌掲載の論文に準じて記述したものであり、既発表の論文・報告書等の転載は認められません。第137回大会のフルペーパーの提出期間は8月20日(月)〜8月27日(月)です。提出日を勘案したうえ応募してください。
(11) ご提出いただいたフルペーパーは、会員に事前にパスワードを送付し、そのパスワードを学会ホームページの大会フルペーパーのサイトに入力する方法で(つまり、インターネ ット上での一般公開という形を避けて)、大会前後の限られた期間にのみ、閲覧と印刷が可能になるようにします。自由論題およびテーマ別分科会で報告が採択された方は、8月20日(月)〜8月27日(月、厳守)で、フルペーパーの電子ファイルを、自由論題、テーマ別分科会それぞれの応募先アドレス(上記のものです)までお送りください。ファイル形式は、原則としてPDFファイルとして、Wordファイルも可とします。ファイルの送付方法や送付先などの詳細については、採択決定後にご連絡いたします。
(12) 自由論題およびテーマ別分科会で報告された会員は、大会での報告後、フルペーパーに改善を加えて、社会政策学会誌『社会政策』に投稿されることを、幹事会と学会誌編集委員会ではつよく奨励し期待しています。大会用フルペーパーは、その後の投稿を考慮してご執筆ください。なお、『社会政策』へ投稿する資格があるのは、会員のみです。
(13) 応募された後で、応募を取り下げること(報告のキャンセル)は、原則としてできません。
(14) 当日のプログラムは企画委員会が決定します。報告時間帯や自由論題のグルーピングについては、複数の分科会にかかわっているなど登壇が重複するケース以外は、応募者からのご希望には応じられません。
(15) 報告申請に先だって当該秋季大会開催年度分の学会費を納入してください。テーマ別分科会の申請者は登壇予定会員全員の当該秋季大会開催年度分の学会費納入を本人に確認してください。当該秋季大会開催年度分の学会費納入状況については申請書に記載欄があります。新規入会者で当該年度の会費請求書がまだ届いていない方を除いて未納であった場合や、記載がない場合、原則として申請書は受理できません。当該年度分の学会費納入が大会プログラム確定時点(第137回大会については5月25日金曜日です)で確認できない場合、その報告や分科会はプログラムには記載されず報告が許可されませんので、ご注意ください。
(16) 共同研究の成果を報告する場合は、共同研究者の了解を取ってください。複数で報告する場合は、応募者のあとに共同研究者(会員・非会員は問いません)の名前をあげ、応募者とともに当日登壇する人に下線を引いて下さい。なお、当日登壇できるのは会員に限られますので、ご注意ください。
秋季大会企画委員会委員長 熊沢 透 (福島大学)
Email:kumat@econ.fukushima-u.ac.jp
第137回(2018年度秋季)大会開催予告
2018年02月28日
秋季大会企画委員会委員長 熊沢 透
日時:2018年9月15日(土)〜9月16日(日)
会場:北海学園大学 豊平キャンパス
- 9月15日(土)書評分科会、自由論題、テーマ別分科会
- 9月16日(日)共通論題
「半福祉・半就労」を考える
- 座長 福原宏幸 会員(大阪市立大)
- 報告者
①吉永 純 会員(花園大学)
②櫻井純理 会員(立命館大学)
③津富 宏 会員(静岡県立大学)
④山村りつ 会員(日本大学)
- コメンテーター 大友芳恵 会員(北海道医療大学)
*自由論題報告、テーマ別分科会の募集日程は以下のとおりです。
- 募集案内の告知 2018年2月28日(水)
- 募集開始 2018年4月13日(金)
- 募集締め切り 2018年5月16日(水)
**第137回大会は開催時期の都合で、第135回大会時より日程が早まっていますのでご注意ください。自由論題報告、テーマ別分科会開催をご申請の方は、併せて「第137回(2018年度秋季)大会自由論題報告、テーマ別分科会の募集について」をご覧下さい。フルペーパー・ファイルの提出期間は8月20日(月)〜8月27日(月)を予定しています。締切の厳守をお願いいたします。
« 次のページ
前の記事 »