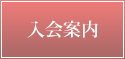2025年05月22日
今年度、研究者育成フォーラム主催の「修論フォーラム」を6月21日(土)に開催します。23年度以降に修士論文を提出された方から、修士論文の内容をご報告いただき、所属大学院以外の社会政策学会の研究者からコメントをいただきます。報告者のみなさんにはその後の学会報告、論文投稿に結びつけていただく機会として、参加者の皆さんにとっても学術交流の機会として、有意義な時間となれば幸いです。
会員でない方も参加可能ですので、大学院生や学部生にもお声がけいただき、研究交流を深める機会としてご利用ください。部分参加も歓迎しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
参加を希望される方は、下記登録先(Google form)に必要情報をご記入の上登録してください。後日、ZoomのURLを送付いたします。
・名称: 社会政策学会25年度修論フォーラム
・開催日時: 6月21日(土)13時~16時20分
・開催方法: オンライン(Zoom)
・参加登録先: https://forms.gle/WNWgpnEeYr7NbFe86
8人の若手研究者による報告が予定されております。
・赤城拓(京都大学大学院人間・環境学研究科)
「子ども期の不利に対して何ができるか―不利の累積メカニズムと不利からの離脱メカニズムの解明—」
・石岡まどか(大阪大学人間科学研究科)
「地域における子どもの育ちとセーフティネットの構築に関する研究—子どもの居場所づくりの地域実践に着目して―」
・坂本珠祈(立教大学コミュニティ福祉学研究科)
「婦人保護施設における若年女性支援に関する考察—女性自立支援施設への転換期における現状と課題―」
・張瑜淳(京都大学文学研究科社会学研究室)
「ヤングケアラーとは誰を指すのか―メディア記事と家族政策の日中比較」
・丁春燁(佛教大学社会福祉学研究科)
「日本におけるソーシャルワーカーの現代的課題 ―『ゆるやかな繋がり』の可能性―」
・渡久地美智留(高崎健康福祉大学健康福祉学部社会福祉学科)
「コロナ特例貸付利用世帯への支援におけるコミュニティソーシャルワーク機能の分析―社会福祉協議会における生活困窮世帯への支援に焦点を当てて―」
・堀田真吾(NTT労働組合 中央本部)
「業務配分と労働時間決定をめぐる個別的コミュニケーションの現状と集団的労使関係の課題」
・八井良汰(一橋大学大学院社会学研究科)
「高度成長期以降の日本の労働市場における『オヤジ』」
2025年05月17日
5月13日衆議院本会議において日本学術会議法案が可決された。日本学術会議総会決議、数多くの学協会の反対声明、研究者・市民の反対行動にもかかわらず採決が強行されたことに強く抗議する。社会政策学会は4月22日に法案に反対し修正を要求する幹事会声明を採択した。日本学術会議会員および多くの学協会と連携し、署名活動、国会議員への働きかけを行った。衆議院内閣委員会で附帯決議がなされたことは反対運動の成果である。また、国会審議を通じて、法案の問題点・不備が浮き彫りとなり、廃案が望ましいことが明らかとなった。社会政策学会第150回大会総会は、衆議院本会議の可決に抗議するとともに、参議院での廃案を要求する。引き続き、日本学術会議・学協会・研究者・市民とともに反対の運動を継続する。
社会政策学会第150回大会総会
2025年05月09日
社会政策学会第150回春季大会(東京都立大学)のフルペーパーを公開しました。
・IDとパスワードはプログラムの5ページに記載されております。
・以下のリンクより閲覧およびダウンロードできます。
1日目
2日目
・フルペーパーの公開期間(2025年5月9日(金)~5月30日(金))
2025年04月30日
9:30〜11:30 テーマ別分科会・自由論題
テーマ別分科会 ② 1-230教室
福祉サービスの質評価と事業プログラム評価
〔一般〕
コーディネーター:埋橋 孝文 (同志社大学・名誉教授、大阪公立大学客員教授)
座長:遠藤 希和子 (金城学院大学)
1.福祉サービスの質と評価システム
埋橋 孝文 (同志社大学・名誉教授、大阪公立大学客員教授) <報告ファイル>
2.福祉サービスの質の向上において第三者評価事業がなぜ役割を果たせないのか
田中 聡子 (県立広島大学) <報告ファイル>
3.プログラム評価からみる親に頼れない若者の独り立ちサポート事業
小田川 華子 (公益社団法人ユニバーサル志縁センター) <報告ファイル>
予定討論者:田中 弘美 (大阪公立大学)
テーマ別分科会 ③ 1-240教室
社会政策における自己決定の諸問題
〔雇用・社会保障の連携部会〕
コーディネーター:高田 一夫 (一橋大学・名誉教授)
座長:佐々木 貴雄 (日本社会事業大学)
1.自己決定の支援をめぐるミクロレベルの実践モデル構想─ある福祉NPO団体の実践から
鈴木 美貴 (立正大学) <報告ファイル>
2.介護保険における自由についての考察
藤島 法仁 (福山平成大学) <報告ファイル>
3.貧困と自己決定
志賀 信夫 (大分大学) <報告ファイル>
自由論題 【 C 】 育児と葛藤 1-210教室
座長:鈴木 恭子 (労働政策研究・研修機構)
1.育児を通した父親のアイデンティティをめぐる葛藤と政策的示唆に関する考察
松村 智史 (名古屋市立大学大学院) <報告ファイル>
2.女性の晩産化とワークライフコンフリクト
内藤 朋枝 (成蹊大学) <報告ファイル>
3.子どもの有無によるコンフリクトを緩和する諸要因の検討―生命保険会社を対象とした調査を元に―
篠原 明穂 (全国生命保険労働組合連合会) <報告ファイル>
自由論題 【 D 】 生活困窮 1-220教室
座長:松原 仁美 (静岡大学)
1.生活困窮者支援制度の利用・認知に結びつく要因
長松 奈美江 (関西学院大学) <報告ファイル>
2.不安定居住予防の類型論に関するレビュー:論点整理と日本における今後の研究課題
河西 奈緒 (国立社会保障・人口問題研究所) <報告ファイル>
11:30~12:45 昼休み
<教育セッション> 社会政策研究とは何か? 1-120教室
座長:瀬野 陸見 (阪南大学)
1.学問としての「社会政策」と私の研究
久本 憲夫 (京都橘大学)
2.社会政策研究のジェンダー化
大沢 真理 (東京大学)
12:45~14:45 テーマ別分科会・自由論題
テーマ別分科会 ④ 1-230教室
韓国の社会福祉サービスの現状と第三者評価
〔一般〕
コーディネーター:埋橋 孝文(同志社大学・名誉教授、大阪公立大学客員教授)
座長:金 圓景 (明治学院大学)
1.日本と韓国における介護保険制度の政策評価―プログラムセオリー評価を中心に―
崔 銀珠 (福山平成大学) <報告ファイル>
2.韓国の福祉サービスにおける評価体制:利用施設を中心に
李 宣英 (国立江陵原州大学 社会福祉学科 <報告ファイル>
3.韓国の高齢者長期療養評価制度が介護サービスの質に与える影響
任 貞美 (慶尚国立大学) <報告ファイル>
予定討論者:金 成垣 (東京大学)
テーマ別分科会 ⑤ 1-240教室
子ども・子育て関連施策における考え方・制度・運用の変遷と、その今日的な意義
〔一般〕
コーディネーター:黒田 有志弥(国立社会保障・人口問題研究所)
1.少子化対策の政策展開:近年の児童福祉の関係に注目して
畑本 裕介 (同志社大学) <報告ファイル>
2.保育所に係る設備及び運営基準の変遷とその意義
黒田 有志弥 (国立社会保障・人口問題研究所) <報告ファイル>
3.子ども・子育てに関わる補助負担金の推移と自治体の行動変化
泉田 信行 (国立社会保障・人口問題研究所) <報告ファイル>
予定討論者:竹沢 純子 (国立社会保障・人口問題研究所)
自由論題 【 E 】 ケア 1-210教室
座長:鈴木 紀子 (日本女子大学)
1.中国におけるケアの再家族化に関する再検討:ダブルケアの視点に基づいて
権 明 (横浜国立大学大学院・院生) <報告ファイル>
2.ケアをしない選択肢を開くための理論的根拠の整理
亀山 裕樹 (北海道大学大学院・院生) <報告ファイル>
3.介護労働者の不足問題と打開策 ―ケアニューデイール政策の導入を―
山中 鹿次 (NPO法人近畿地域活性ネットワーク) <報告ファイル>
自由論題 【 F 】 障害者 1-220教室
座長:田宮 遊子(神戸学院大学)
1.障害者雇用促進法における「障害者」の理念と課題―ハローワーク実務に対する調査から―
寺田 岳 (一橋大学国際・公共政策大学院修了) <報告ファイル>
2.精神障害による年金受給者が生活保護を併給しないために必要な年金水準
およびその就労率への影響:生活水準(SoL)法と実態費用法に基づく試算
山田 篤裕 (慶應義塾大学)・百瀬 優 (流通経済大学) <報告ファイル>
15:00~17:00 テーマ別分科会・自由論題
テーマ別分科会 ⑥ 1-230教室
東京山谷における生活困窮者の来歴と支援の特質
〔一般〕
コーディネーター:原田 玄機(高崎経済大学)
座長:猪飼 周平(一橋大学大学院)
1.生活や就労の基盤喪失時の政策支援の困難性 ――山谷地区での聞き取り調査からの示唆
岡本 武史 (一橋大学・院生)・原田玄機 (高崎経済大学)
半田 諒志 (一橋大学・院生)・孫宜燮 (一橋大学・院生) <報告ファイル>
2.山谷地域はいかに「福祉の街」となったのか
孫 宜燮 (一橋大学・院生) <報告ファイル>
3.山谷地域における就労支援:
ホームレス経験者を含む生活困窮者を対象とした「ケア付き就労支援」の実践
半田 諒志 (一橋大学・院生) <報告ファイル>
予定討論者:後藤 広史 (立教大学)
自由論題 【 G 】 介護保険・年金 1-210教室
座長:鈴木 美貴 (立正大学)
1.介護保険制度における保険料負担と介護費用の地域差に関する分析
―Jaccard係数と階層的クラスタリングによる類型化の試み―
石田 真 (大阪公立大学大学院・院生) <報告ファイル>
2.なぜハイブリッド型年金はアメリカで定着しなかったのか?:CBプランをめぐる紛争を中心に
吉田 健三 (青山学院大学) <報告ファイル>
自由論題 【 H 】 子ども 1-220教室
座長: 近間 由幸(鹿児島県立短期大学)
1.子どもの放課後の過ごし方に関する実証研究:自治体統合データを用いたクラスター分析
松原 祥 (東京都立大学大学院・院生) <報告ファイル>
2.健康観察アプリデータを使用した不登校児童・生徒の分析
加藤 穂高 (福島大学) <報告ファイル>
3.子どもの家庭における意見尊重:子ども回答による大規模アンケート調査からの分析
新田 凌大 (東京都立大学大学院・院生)・青木 健資 (東京都立大学・院 生・非会員)
荻原 環 (東京都立大学・院生・非会員)・ 松原 祥 (東京都立大学・院生)
近藤 天之 (東京都立大学・院生)・ 阿部 彩 (東京都立大学) <報告ファイル>
自由論題 【 I 】 職業キャリア 1-240教室
座長:郭 芳(同志社大学)
1.タスクの構造と価値の変動 ─昇進に寄与するタスクに着目して─
瀬戸 健太郎 (立教大学)・那須 蘭太郎 (東京大学・院生) <報告ファイル>
2.“日本的民主観”による「徒弟制度」への偏見の問題─職業教育訓練低迷の一要因としての─
田中 萬年 (職業能力開発総合大学校・名誉教授) <報告ファイル>
自由論題 【 J 】 政策の決定・影響 1-110教室
座長:中村 天江 (連合総合生活開発研究所)
1.EBPMに向けた基本的課題─評価先行、統計偏重・定性調査の軽視、調査員を巡って─
西村 幸満 (国立社会保障・人口問題研究所) <報告ファイル>
2.最低賃金の決定プロセス ─地方連合会13組織の事例分析
前浦 穂高 (労働政策研究・研修機構)・西村純(中央大学) <報告ファイル>
3.ポストコロナの感染症意識:社会的要因を探る
高橋 義明 (明海大学) <報告ファイル>
2025年04月30日
9:30〜11:30 テーマ別分科会・自由論題
テーマ別分科 ① 1-230教室
アジアの高齢社会における高齢者の所得保障 〔アジア部会〕
座長:朱 珉 (千葉商科大学)
1.中国における農村年金保険の政策目標と挑戦
趙 徳余 (中国・復旦大学) <報告ファイル>
2.日韓における高齢者関連政策の比較分析
―労働政策と社会保障制度及び自助努力の促進が経済社会に与える影響
金 明中 (ニッセイ基礎研究所・亜細亜大学) <報告ファイル>
予定討論者:沈 潔 (日本女子大学・名誉教授)
自由論題 【 A 】 ジェンダー 1-220教室
座長:堀川 祐里(新潟国際情報大学)
1.日本のマスメディアにおける取材対象との関係性構築とジェンダー
佐藤 千矢子 (埼玉大学大学院・院生) <報告ファイル>
2.「からゆきさん」から見る日本の性暴力
賈 瑩瑩 (千葉大学大学院・院生) <報告ファイル>
3.女性支援における対象の包括性の課題:交差性の視点からの「女性支援事業」の考察
高橋 麻美 (お茶の水女子大学大学院・院生) <報告ファイル>
自由論題 【 B 】 地方の仕事・暮らし 1-240教室
座長:中澤 秀一 (静岡県立大学)
1.地方圏における元プロ選手の多様な暮らし方とその課題─「スポーツまちづくり」事例を中心に─
呉 ハヌン (大分大学大学院・院生) <報告ファイル>
2.大都市圏から地方圏へ回帰する理由としての家業継承とその後
─岩手県出身の若者の生活史調査から
杉田 菜花 (大阪市立大学大学院・院生) <報告ファイル>
11:30~13:00 昼休み
13:00~17:00 共通論題
男女賃金格差を改めて検証する 6-110教室
座長:清山 玲 (茨城大学)
報告1 どうしたら男女賃金格差は縮まるのか
田中 洋子 (筑波大学・名誉教授、ベルリン自由大学フリードリヒ・マイネッケ 研究所
・法政大学大原社会問題研究所客員研究員) <報告ファイル>
報告2 残業時間の賃金プレミアム ―男女格差と経年変化の分析―
児玉 直美 (明治学院大学・非会員) <報告ファイル>
報告3 非正規雇用の賃金制度はこの10年でどう変わったか
―小売業の聞き取り調査から賃金格差を考える―
小野 晶子 (労働政策研究・研修機構) <報告ファイル>
コメンテーター:遠藤 公嗣 (明治大学・名誉教授)
ディスカッション・総括
17:05〜18:05 総会 6-110教室
18:30−20:15 懇親会 国際交流会館
2025年04月26日
日本学術会議法案について、当学会を含む数多くの学協会が反対・修正を求める声明を発表しております。4月13日の日本学術会議第一部会・社会学委員会の会員による説明会に参加した学協会有志を中心に署名活動が提起されました。このたび署名活動のホームページが開設されましたので、皆様にお知らせするとともに、賛同される方の署名を求めたいと思います。また、「社会学・社会福祉学・社会政策学」以外の研究者・院生の方にも拡散していただきたく願います。
「日本学術会議法案の修正を求める社会学・社会福祉学・社会政策学研究者有志ホームページ」
この署名は4月30日正午にいったん集約・印刷し、国会に郵送する予定です。
なお、国会では、内閣委員会で4月25日に続いて5月7日に審議し、9日に本会議で審議される見通しだとのことです。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
4月26日
社会政策学会代表幹事 菅沼隆
2025年04月22日
社会政策学会幹事会は、4月18日に国会に提案された「日本学術会議法案」に反対し、修正をもとめる声明を採択しました。会員の皆様にお知らせします。声明を衆議院内閣委員会各委員に送付するとともに、他の学協会と連携し、取り組みを進めて参ります。
声明
社会政策学会は、日本学術会議法案に反対し、国会に対し修正を求めます。同法案は、日本学術会議が2021年4月総会で提示した「ナショナル・アカデミーの5要件」を満たしていません。また、2024年7月会長声明で表明された「5つの懸念点」も払拭されていません。私たちは、法案の修正を求めた日本学術会議総会決議(2025年4月15日)に賛同します。
2025年4月22日 社会政策学会幹事会 代表幹事菅沼隆
2025年04月08日
会員の皆さま
社会政策学会第150回大会は、東京都立大学にて、5月17日・18日に開催されます。
参加申し込み(+お弁当、懇親会申し込み)
サイトがオープンとなりましたので、
こちらからお申込みください。